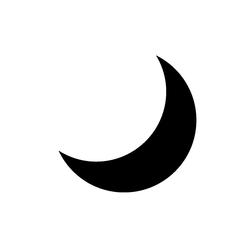11 / 11
ミラノ・コンチェルト③
「大変だったな、ハヤト。今度頭のおかしな奴に絡まれたら、すぐにオレを呼べ」
隼人の目を正面から見据えながら、ロミオは真剣な顔で言い切る。その姿は大変に頼りがいがあり、隼人も目尻をゆるませたが、モデルのように華やかな顔立ちをしていても、中身は地中海の真夏の太陽よりも熱いイタリアの男である。恐らくそのような場に呼んだらどうなるかは容易に想像ができるので、よほどのことがない限り気持ちだけをありがたく受け止めておくことにした。
「何だよ、ハヤト」
「いや」
どんな表情をしていても相変わらず可愛いなあと、マグカップを片手にロミオにうっとりする隼人である。笑った顔は勿論、怒った顔も困った顔も真面目な顔も、洩れなく可愛くて仕方がない。自分がロミオを怒らせている時ですら見惚れている隼人である。当のロミオが知ったら怒るか呆れるか、または喜ぶか恥ずかしがるかは不明だが、今は不思議そうに眉をしかめた。
「そんなにコーヒーが美味しいのか?」
「ああ、とっても美味しいよ。ロミオが淹れてくれたから」
今日一日の疲れがコーヒーのまろやかな味の中で蕩けていく。隼人は肩肘をついて、幸せだなあとじんわりしながらロミオを見つめた。
「ハヤトが喜んでくれるなら、オレも嬉しいけどね」
自分で淹れたコーヒーには自信があるロミオである。隼人に褒められたので笑顔になった。
「それに、今夜のオレはとても気分がいいんだ」
「それは良かったよ」
「どうしてだと思う?」
ロミオは謎々のように問いかける。その青みがかった海のようなエメラルド色の瞳には、からかうような色合いに混じって、わずかに熱っぽさが垣間見える。
「どうして……うーん」
木製の平たいテーブルにマグカップを静かに置くと、隼人は真面目に頭をひねった。
「そうだな……きっと何か嬉しいことがあったんだな、ロミオ」
「そうさ。オレはとても嬉しい」
「うーん、その、ロミオの職業で、何かいいことでもあったのかな?」
隼人は首をひねりながらも、遠慮がちに口にする。ロミオはゲイポルノ俳優だ。しかもその界隈では非常に有名で人気がある。隼人がロミオの仕事を知った時は腰を抜かさんばかりに驚いたが、付き合い始めてからはなるべく職業に関しては聞かないことにしていた。隼人なりの配慮であるし、それ以上に個人的にはあまり知りたくなったからだ。
「違う、ハヤト。そうじゃない」
仕事第一の隼人らしい言葉に、ロミオは椅子の上でおかしそうに笑う。
「今夜、ハヤトと会えたから気分がいいんだ。オレにとっては、とても大切なことだ」
「……あ、そ、そうか」
あまりに率直に言われて、隼人は照れる。
「そうさ」
ロミオはテーブル越しに身を乗り出すと、熱い視線をおくる。
「オレが一番幸せなのは、ハヤトと一緒にいて、コーヒーを飲んだり、パスタを食べたり、お喋りをすることだ。ハヤトとたっぷりとキスをして、セックスをする。それが俺には最高の一日なんだ」
「……そ、そうか……」
隼人は壊れたラジオのように同じ文句を繰り返した。ロミオはいつも眩しいくらいにオープンだ。付き合うようになってからだいぶ慣れたとはいえ、やはりまだ気恥ずかしくなってしまう。自分もロミオのように己の感情をありのままに口に出せればよいのだが、日本人としての性 なのか、イタリア人のようにはできない。好きだと言葉に出すのも照れてしまう。ロミオは息を吸うように自分へ言ってくれるのだが。
――俺も気の利いた言葉の一つでも出てくればなあ……
隼人は自分自身にため息をつきながらも、黙って視線だけをロミオへ向けた。
「おい」
ロミオがおどける。
「そんなに熱心に見つめられたら、オレはジェラートのように溶けてしまうぞ」
「あ……ああ、すまない、ロミオ」
慌てて目を逸らす。
「ハヤトに見つめられるのは嫌いじゃない。オレは大好きさ。もっともっとオレを見つめて欲しい。ずっと、死ぬまでね」
ロミオは小首を傾げて、隼人を上目遣いにうかがう。
「どう? オレの誘い方」
「……どうって……」
心拍数がぴょんと跳ね上がる。ロミオはとっても色っぽい男なのだ。本人もわかっていると思うが。
「オレが散々だった今日のハヤトのラストを飾ってやるよ」
ロミオはわかるだろうと言いたげに、隼人の困惑めいた目を覗き込む。
「最高の一日にしようぜ」
しかし鈍い隼人には通じていない。
「一日って、もう終わるんだが……」
会社から直行したのでスーツ姿である。革製の腕時計の針は九時を回っている。
「だからさ。一日が終わる前に、オレと最高の時間を過ごそうぜ、ハヤト」
ロミオの声からは誘うようなじれったい響きがある。
隼人の頬がほんわりと火照った。ようやく意図がわかった。
「そ、そうだな」
どうしてこんなにロミオは可愛いんだろうと浮かれながら、気持ちが昂ってきた。そわそわする心に引きずられるように、海の花のような色彩のサファイアブルーのネクタイをゆるめて、上着を脱ごうとした。
「待て、ハヤト」
ロミオが手を伸ばして止める。
「オレが脱がしてやる。あっちでな」
奥の寝室を、親指を曲げて指す。
「うまく脱がしてやる。オレはプロだから」
ロミオは椅子から意気揚々と立ち上がると、隼人にも同じく促す。隼人は誘われるままに腰をあげた。
「その、ロミオ」
「何だ」
隼人は指先で頬を軽く掻く。
「まずはシャワーを浴びたいんだが……いいかな?」
今日一日の汚れを落としてからロミオとベッドに入りたい。欧米人は行為の前にあまりシャワーを浴びたりはしないようなのだが、隼人を通じて日本人の清潔っぷりを知ったロミオは、しょうがないというように笑った。
「いいぜ。その代わり、オレも一緒にシャワーを浴びるからな」
そう言うと、隼人の肩に腕を回して顔を近づけると、頬にキスをした。花のような良い匂いがふわりとロミオから漂ってきて、隼人の頬が崩れるようにゆるむ。
「俺がロミオの身体を綺麗に洗うよ」
「じゃあ、オレもハヤトの身体を洗ってやる。楽しみだな」
二人は仲良くお喋りをしながら、バスルームへ向かった。
数日後、イラーリオの事務所を訪ねた隼人とジュリアーノは、カーデザインの最終的な話し合いをした。イラーリオから渡された新たなデッサンを見て、隅々までチェックする。先日のデザインがさらに修正され、より洗練された形になっていた。これならばサガノ本社でもゴーサインが出るに違いないと隼人は確信した。
「とても素敵です、イラーリオ。すぐに本社と連絡を取ります」
隼人は両手にあるデッサンを見ながら、少々興奮気味に喋る。隣のジュリアーノも「ファンタスティコ!」と喜んでいる。
「ありがとう! このようなデザインを生み出せて私も最高に幸せだ!」
イラーリオも目の前の二人の反応にいたく満足したようで、ルチアーノ・パヴァロッティさながらのテノールを響かせて高揚感を爆発させる。
「今の私が生み出した最高のデザインだ! 明日には私はまた新たなデザインを生み出すだろう! だがそれは明日の話だ! 今は今の至福を存分に味わうんだ! さあ! 一緒にワインを飲もう! この素晴らしい時間を高らかに祝おう!!」
高級感溢れる革張りのソファーから勢いよく立ち上がると、オペラでも歌っているような口調で何やら一人で喋りしながらワインを取りに奥の続き部屋へ向かう。ここまで上機嫌のイラーリオを見るのは始めてで、隼人も嬉しくなった。
「俺はちょっと席を外すぞ」
ジュリアーノがそそくさと腰を浮かせる。
「どうした?」
「素晴らしい時間を一緒に過ごしに行くんだよ、女神とね」
わかるだろうとウィンクをして、足取り軽く室内を後にする。隼人は苦笑いした。モニカに会いに行ったのだろう。まあいいかと、再びデッサンに目を落とした。
ともだちにシェアしよう!