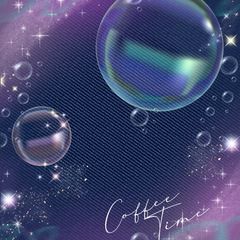2 / 79
彼の正体
少しだけキツめに包帯を巻き、無事に応急処置を終えた。
「ふぅ……っ」
「其方のおかげで助かった、礼を言う」
さっきまでは彼の怪我が気になって無我夢中だったけれど、彼の言葉に一気に頭が冷静になってくる。
勢いで家にまで連れてきちゃったけど、僕は彼のことを何一つ知らない。
「あ、あの……」
あなたは一体どこの誰なんですか?
そう聞こうとして、さっき彼に言われたことを思い出す。
――人に名を尋ねるときはまず己から名乗るものだと思うが。
とりあえず聞きたいことは山のようにあるけれど、僕のことを信用してもらわないと話してはくれないかもしれない。
「あの、僕は……七瀬 智己 と言います。ここから少し離れた喫茶店でアルバイトをしています。あの、あなたのことを尋ねてもいいですか?」
嘘は言っていませんよ……と彼の目を見ながら話しかけると、彼はバツが悪そうな顔を向けた。
「ああ、いや。さっきは申し訳なかった。私も突然のことで混乱していたのでな」
ああ。
さっきまでの口調とは変わって、少し優しげな感じに変わった。
僕のことを信用してくれたのかなと思うと、少し嬉しかった。
「いいえ、気にしないでください。怪我もしていたし、慌てるのも無理はないですよね」
「あ、ああ。そうだな……」
「それであの、その怪我はどうしたんですか? 喧嘩ですか? もし、襲われたなら警察に連絡しないと!」
「怪我は気にすることはないが、警、察とは……それは騎士団のようなものか?」
「騎士、団? 警察は警察ですけど……その、悪い人を捕まえるところです」
「ふむ。ならば、連絡するのはやめておいた方がよさそうだ。其方も信じてくれるかはわからぬが、どうやら私は別の世界へと飛ばされてきたようだ」
「へっ? 別、世界……ですか?」
彼は急に何を言い出したのだろう?
もしかして、映画の登場人物になりきってるとか?
これは話に乗ってあげるべき?
いや、でも僕は……演技なんてできそうもない。
「えっと、あ、あの……きっと怪我をして混乱しているんですよね。僕は気にしませんから、好きなだけここで休んでいってください。狭いですけど、好きに使ってもらって大丈夫ですから……」
「いや、怪我をしたせいで頭がおかしくなったわけではない。まぁ、私自身、まだ信じられずにいるのだから其方が信じられぬのは当然だろうな。だが、これから私が話すことは全て事実だ。それを其方が信じるかは任せるとしよう」
僕の目をまっすぐ見つめながら、深呼吸した彼はゆっくりと口を開いた。
「私はクリスティアーノ・バーンスタイン。ビスカリア王国騎士団で騎士団長を務めている」
「ビ、ビスカリア、王国……騎士、団長……」
彼の口から出てきたのは聞きなれない言葉ばかり。
驚きすぎて彼の言葉を鸚鵡返しするしかできない。
「そうだ。おそらくこの世界に私の国はないのだろう?」
「は、はい。多分……」
「だが、全て事実だ。私は騎士団の訓練を終え、帰宅途中に暴漢たちに剣で切りつけられた。この傷はその時のものだ。暴漢を全て倒し終えたまではよかったが、突然眩い光に包まれ、気づいたら先ほどの場所に立っていたのだ」
「そ、そんなことが……」
「あまりにも突飛なことだと思うだろう。だが、私は嘘偽りなど一切申していない」
彼の話していることは到底信じられそうにない。
でも、彼の言葉に僕を騙そうなんて気持ちはどこにも見当たらないのは事実だ。
それどころか、真摯に僕に伝えようとしているようにしか見えない。
でも……王国の騎士団長が異世界からやってきて、僕の目の前に現れるなんて……。
そんなことありえる?
だけど……彼が嘘をつく理由なんてどこにあるんだ?
そもそも、ありえないとは絶対に言い切れないじゃないか。
だってどんなことだって起きる可能性はゼロじゃない。
父さんと母さんが事故で亡くなったのだって僕にとっては信じられない、ありえない出来事だった。
でもそれだって起きてしまった……。
なら、僕は彼のいうことを信じよう。
彼がもし嘘をついていたとしても、僕は自分が信じたことに後悔しない。
彼がどうであれ、困っているなら助けるのが人としての務めなんだから。
「あの、じゃあ……ここに好きなだけいてください。もしかしたら、何かのきっかけであなたの世界に帰れるかもしれませんから……」
「――っ、信じてくれるのか?」
「はい。僕はあなたを信じます」
「ありがとう、本当に……感謝する」
「じゃあ、えっと、バーンスタインさん。何か着替えをお出ししますね」
「ありがとう。ああ、私のことはクリスと呼んでくれ」
「えっ、でも騎士団長さんを愛称で呼ぶなんて……」
「何を言っている? 君は私の命の恩人なのだから堅苦しく呼ぶ必要なんてない。そうだろう?」
「は、はい。じゃあ、クリスさん。僕のことは智己と呼んでください」
「わかった。トモキ……良い名だな」
「あ、ありがとうございます。あの、着替え取ってきますね」
なんだか自然に名前を褒められてドキドキする。
僕は赤くなった顔を隠すように急いでリビングから飛び出した。
ともだちにシェアしよう!