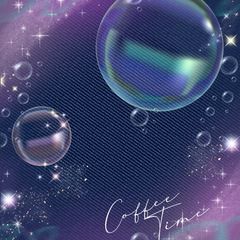18 / 85
おかしくなりそう!
「じゃあ、大智さん。どうぞ」
「――っ!!」
いきなり蕩けるような笑顔で桃を差し出してきた。
「じ、自分で……」
「ほら、汁が垂れちゃいますから」
「あっ――!」
そう言われたらもう素直に口を開けるしかない。
「ふふっ。良い子ですね」
今までよりもずっとずっと甘い声がかけられながら、俺の口の中に桃を入れてくれる。
その声にドキドキしすぎて桃の食べ方も分からなくなってしまったのか、唇の端からとろりと汁が垂れてしまった。
慌てて手で拭おうとすると、さっとその手を握られて代わりに透也くんの長い指が近づいてきた。
「――っ!」
俺の唇から垂れていた桃の汁は、透也くんの指から彼の口の中に移動してしまっていた。
「い、いま……」
「ふふっ。甘かったですよ。ご馳走さまです」
「ご、ちそうさま、って……」
「だって、せっかくのご馳走を溢したらもったいないでしょう?」
「あれが……ご馳走?」
「はい。当然でしょう? 本当は舌で舐め取りたかったんですけどね。流石に我慢しました」
「舌で、って――っ!! それって……キス?」
うそっ!
さっき告白されたばっかりなのに、もうキス?
「はい。えっ? もしかして、舌の方が良かったですか?」
「――っ!! そんな……っ!」
「ふふっ。大丈夫ですよ。大智さんの方からキスをねだってくるくらい、たっぷり愛して見せますから」
パチンと綺麗なウィンクをされてまたドキドキさせられる。
透也くんに聞こえてるんじゃないかと思ってしまうくらい、心臓が激しく動いてる。
これ以上にたっぷりなんて……俺の身が持たないかも……。
ああーっ、もう!
どうすれば良いんだよ!!
あまりにもいろんなことが起こりすぎて頭の中がおかしくなりそう。
興奮しすぎて喉が渇いてしまった俺は、目の前にあったグラスを手に取りグイッと傾け一気に飲み干してしまった。
「あっ、大智さん! それっ!!」
透也くんが俺を制する声が聞こえた気がしたけれど、もうその時には目がぐるぐると回っていて自分ではどうにもできなくなってしまっていた。
フッと目の前が真っ暗になったと思ったら、俺は温かい何かに包まれた気がした。
「う……ん、いたたっ――」
感じたことのないような頭の痛みに目を覚ました。
あれ? ここ、どこだっけ?
でも何だかすごくあったかくて気持ちがいいんだけど……。
頭の痛みに目が開けられずにいたら、優しく頭を撫でられる。
なに、これ……すごく優しい手。
さっきまでの頭の痛みが和らいでいく。
こんなの初めてだ。
「大智さん、大丈夫ですか?」
あまりの心地よさに、もっと撫でて欲しくて顔を擦り寄せていると、優しくて蕩けるような甘い声が頭上から聞こえてきた。
「えっ? ――った!」
びっくりして顔を上げようとしたと同時にさっきの頭の痛みがまた襲いかかってきた。
「ほら、無理しちゃダメですよ」
「この声……えっ、透也くん? なんで、ここに?」
「昨日のこと、忘れてしまいましたか?」
「えっ、昨日って……」
「大智さん、グラスに入れていた白ワインを一気飲みして倒れちゃったんですよ」
「あ――っ!」
確かに飲んじゃった気がする。
「びっくりしましたよ。大智さん、こんなにお酒に弱かったんですね」
「いや、そうでもないはずなんだけど……」
「もしかして、あの時私にもう酔っちゃったからとか?」
「えっ? 透也くんにって――あっ!!!」
――本当に私は大智さんが好きなんです。私が全部忘れさせてあげますから……。これからたっぷり好きにならせてみせますから。覚悟しておいてくださいね。
昨日、そう言われたんだっけ……。
じゃあ、本当に俺は、透也くんの恋人になったってこと?
「ふふっ。やっと思い出してくれました? 私の可愛いハニー」
「は、ハニーって……透也くんって、恋人にいつもそう言うこというの?」
「さぁ……初めてですから、わかりませんけど大智さんには言いたくなりました。だって、どこもかしこも甘い匂いがしますよ」
「そんなこと……っ」
「ふふっ。本当に可愛いですね、大智さんは。可愛すぎてどんどん手放せなくなります」
こんなふうに愛を伝えられたのって初めてだ。
しかもこれが上べだけじゃないことを全身から感じる。
でも……いつか、宏樹みたいにどんどん気持ちが冷めていったら?
もう、俺は二度と立ち直れないかもしれない。
「大智さん?」
「あ、ああ。ごめん」
「また何か変なこと考えてないですか?」
「えっ? 変なことって?」
「ふふっ。覚えてないんですね。昨日、ワイン一気飲みして倒れちゃって、呼吸は安定してたからとりあえず寝かせておこうと思ってベッドに連れていったら、『いつか目の前からいなくなるなら、優しくしないで……』って言ったんですよ」
「そんなことを?」
「ええ。でも、そんなこといいながら、私の手は全然離さなくて……本当可愛かったですよ」
「うそ……っ、恥ずかしいっ!」
「あれが大智さんの気持ちですよね? 私と一緒にいたいと思ってくれているはずです。言っときますけど、私は一生手放すつもりなんてないですから! 今、会社にもロサンゼルス支社に異動願を出してるんです」
「はっ? 異動願、って……えっ?」
思いがけない透也くんの言葉に一気に酔いも頭の痛みも飛んでいったような気がした。
ともだちにシェアしよう!