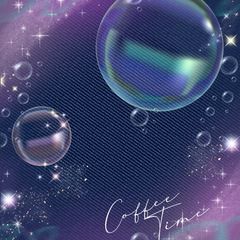36 / 85
透也の笑顔
トプトプと口の中に溜まっていく精液をどうしていいかわからなくて、俺はそのままゴクンと飲み尽くし、ゆっくりと透也のモノを口から引き抜いた。
「えっ――?!」
俺の喉が動いたことに気づいた透也が驚愕の表情で俺を見つめる。
「あ、あの……と、うや?」
「もし、かして……い、ま……のん、だんですか?」
「えっ、うん……のん、だけど……だ、めだったのか?」
口で咥えるということまでは知っていたけど、最後どうするのかまでは知らなかったんだ。
じゃあ、あれはどうするのが正しかったんだ?
「あの……大丈夫ですか?」
「えっ? ああ、うん。不思議な味だけど、透也のなら嫌な気はしないし、別にお腹も痛くないから大丈夫だとは思うけど……」
「――っ!! ああ、もうっ! 本当に大智は……」
「なんか、ダメだったか?」
「違います、逆ですよ。俺をこれ以上嬉しがらせてどうするつもりですか?」
「嬉しがらせるって……」
透也の言っていることがいよいよわからなくなってきたけど、
「こんな幸せな朝を迎えたのは生まれて初めてです。なんて言っても、大智が朝から俺のを可愛がってくれたんですからね」
と嬉しそうに抱きしめられる。
「あ、これ飲んでください」
ベッド脇に置かれた小さな箱型のものはどうやら冷蔵庫だったらしい。
長い腕を伸ばしてそこからペットボトルの水を取ると、さっと蓋を開けて飲ませてくれた。
喉が渇いていたらしい俺はあっという間に三分の一ほどを飲み切った。
「ふぅ、美味しい」
「ふふっ。これで朝の挨拶ができます」
「朝の挨拶?」
「ええ」
透也はにっこり笑うと、そのまま唇を重ね合わせてきた。
唇を何度も啄む軽いキスをすると、ゆっくりと唇を離した。
「大智とのキスはいつでも最高ですけど、流石に自分の精液は積極的には口にしたくないですからね」
「ああ、それでわざわざ水を?」
俺の言葉にいたずらっ子のような笑みを見せる透也がなんとなく可愛くて、思わず笑ってしまった。
「笑い事じゃないですよ。大体びっくりしましたよ。目が覚めたら大智があんなことしてるんですから」
「いや、勃ってたから……その、出してあげないと辛いかと思って……勝手に悪い……」
「いやもう、嬉しすぎるし気持ち良すぎるしで、知らない間に天国に行ったと思いましたよ。本当、こんな朝の目覚めなら毎日でもお願いしたいくらいですよ」
「えっ? 毎日?」
「ふふっ。冗談です」
「いや、別に勃ってるなら辛いだろうし、いつでもしてあげていいんだけど……」
「――っ、これ以上、煽られたら本当にやばいので……っ、この話はその辺にしときましょう」
「えっ? ああ、そうだなじゃあ、そろそろ起きようか。って今、何時ごろだろう?」
話題を変えるように時計を探してみれば、まだ朝の7時前。
よかった。
まだゆっくりと朝の時間を過ごせそうだ。
「大智は先に洗面所使っていいですよ。俺はキッチンに寄ってから身支度を整えますから」
「ああ、わかった。ありがとう」
透也はさっとガウンを羽織り、俺にもお揃いのガウンを手渡した。
「これ……」
「昨日はシャワーを浴びてからそのまま寝たので、起きた時用に用意しておいたんですよ」
こんなところまで準備がいい。
やっぱさすがだな。
俺はお揃いのガウンを羽織り、洗面所に向かった。
手早く身支度を整え、キッチンに向かうと、今日もまた出汁のいい匂いがしてきた。
「ああ、いい匂いだな。本当に日本にいる時より出汁の匂いを嗅いでいる気がするよ」
「ふふっ。もう大智の胃袋は掴んでますから、誰の手料理も食べられないようにしてあげます」
「透也のしか食べられなくなると、透也が帰国した時が怖いな」
まだ二ヶ月も先だけど、その時には今よりももっと透也の食事しか受け付けなくなっているかもしれない。
「大丈夫です。できるだけたくさん冷凍していきますし、どうしても我慢できない時は兄貴の店に行ってください」
「あのお店に? でも、そんな通ったら迷惑じゃないか?」
「他の店に行くよりはマシです。あそこなら大智の健康にも申し分ないので」
「さすがお兄さんのことを信用しているんだな」
「まぁ、料理の腕は正直変わらないと思ってますけど、俺がいない間、大智を任せられるのは兄貴だけだと思ってますよ」
にっこりと微笑む透也を見ていると、なんだか少し心が痛い。
だからつい自分の胸の内を言ってしまった。
「そうだな。鰻は日本で食べてた時より美味しかったし、他の料理も美味しそうだったけど……俺は、多分透也の料理が一番好きだから、俺をお兄さんに任せないで早く帰ってきてくれ」
「――っ、大智っ!! はい。わかりました。早く帰ってくるって約束しますね」
嬉しそうに笑うその表情は、俺の大好きな透也そのものだった。
ロード中
ともだちにシェアしよう!