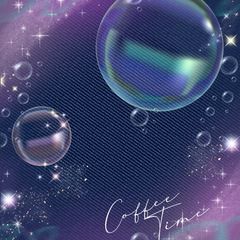4 / 33
美味しい朝食
「……佐美くん、宇佐美くん」
「うーん、もう、ちょっと……」
「ふふっ。寝かせてあげたいけど、そろそろ起きて準備を始めたほうがいい」
「えっ?」
びっくりして布団を捲り上げ、飛び起きると目の前に見覚えのあるイケメンがいる。
えっと、この人は……
「どうした? まだ寝ぼけてる?」
ニコッと笑った顔が上田に似ていて、その瞬間僕は昨夜のことを思い出した。
「あっ! すみません、僕……」
「いいよ。昨日のことも忘れるくらい熟睡したってことだろう? それなら安心したよ。さぁ、顔を洗っておいで。ご飯ができてるから」
「あ、はい。ありがとうございます」
洗面所で顔を洗い、鏡に映った僕は驚くほどスッキリした表情をしていたことに気づいた。
由依に裏切られてメンタルもボロボロだと思ってたのに……夜中だって一度も起きなかったしものすごく熟睡できたな。
ホテルに行ってたらきっと眠れない夜を過ごしたかも。
僕には何の落ち度もない。
何も気にすることはない。
誉さんがそう言ってくれたから落ち着けたのかも……。
彼がこれから先、僕の味方になってくれるのは本当に心強い。
上田にはいい人を紹介してもらって助かったな。
顔を洗って、リビングに戻るといい匂いが漂っている。
その匂いに反応するようにお腹がグーッと勢いよく鳴ってしまった。
そういえば、昨日は仕事中にちょっと摘んだだけだった。
誉さんにお腹の音を聞かれたかもと思うと恥ずかしくて居た堪れなくなっていると、
「お腹が空いたのならよかった。昨日は食事も取れそうにないほど顔色が悪かったからね。それで飛行機に乗せるの心配だったんだよ」
と嬉しそうに言ってくれる。
ああ、誉さんって本当に僕のことを心配してくれていたんだ……。
そう思うだけで心の奥が温かくなっていくのを感じた。
「わぁーっ! 美味しそうっ!!」
誉さんの用意してくれた食事は THE•日本の朝ごはんとでもいえそうなほど、綺麗な和定食。
炊き立てほかほかのご飯に、長ネギと豆腐の味噌汁、銀鱈の西京漬に、美味しそうな卵焼き。わかめときゅうりの酢の物にきんぴらごぼうまで綺麗に盛り付けられていて、見ているだけで涎が垂れてしまいそう。
「アメリカに長期出張中だと聞いていたからね、きっと和食が恋しくなっている頃だと思って和食にして見たんだが、気に入ってくれて嬉しいよ」
「はい。もうずっとハンバーガーやらピザばっかりで飽きてたんです。でもまさか、こんな美味しそうなご飯を用意してもらえるなんて!!! 誉さん、料理お上手なんですね」
「ふふっ。そんなに言われると照れるな。さぁ、温かいうちに食べてくれ」
そう言われて、僕はまず味噌汁に手を伸ばした。
「んっ、美味しいっ!!」
空きっ腹に、出汁のよく取れた味噌汁がじわじわと広がっていく。
本当に美味しい。
こんなに美味しい味噌汁を飲んだのはいつぶりだろう……。
そういえば、由依は味噌汁は苦手だからと言って、いつもインスタントの味噌汁だったっけ。
――味噌汁とか、あってもなくても変わらなくない? その分、おかずには手間かけるって。
そう言って出してくれた由依の手料理が宅配サービスで届けられたものだということは薄々気づいていた。
それでもぼく自身が料理ができないのに、由依を責めることはできなかった。
割高でも、疲れて帰ってきて食事を用意してくれるだけいい。
それくらいできるくらいには稼いでいるつもりだったから。
でもまさか、そのせいでATMと思われていたなんて思わなかった。
「……佐美くん? どうした?」
「えっ? あっ、ごめんなさい」
「味噌汁、口に合わなかったかな?」
「いいえ、そんなこと……っ、ちょっといろいろ思い出してしまって……。味噌汁ってこんなに美味しいものだったんですね。なんか毎日飲みたくなっちゃうな」
「ふふっ。いいよ。宇佐美くんのためならいつだって作るよ」
にっこりと笑顔を向けられて、ドキドキしてしまう。
「あ、いや。そんな……あ、あの誉さんも冗談とか言うんですね。意外です」
「冗談じゃないんだけどね。まぁ、いいか。ほら、他のおかずも食べてみて。この銀鱈はアメリカでは食べられないよ」
「は、はい。いただきます。わっ! すごく美味しいっ!!」
ほかほかのご飯と一緒に美味しい銀鱈を頬張りながらも、さっきの誉さんの言葉が耳から離れなかった。
冗談じゃないってどう言う意味なんだろう?
そんなことを考えながらも、お腹が空いていた僕はあっという間にご飯を完食した。
「ふぅー。お腹いっぱいです」
「満足してくれて良かったよ。はい、お茶どうぞ」
「あ、ありがとうございます」
手に馴染む湯呑みを手渡され、一口啜るとさっぱりとした口当たりに甘味も旨味も感じられてすごくおいしかった。
「このお茶、すごく美味しいですね」
「だろう? 私のお気に入りのお茶でね、九州の友人に送ってもらっている『白折茶』なんだ。アメリカではなかなか飲めないだろうからね」
「すごい! こだわりのお茶なんですね」
「いや、料理に合う飲み物を突き詰めて行ったらそうなったんだよ。料理はフレンチでもイタリアンでもなんでも得意だから、今度は和食以外も振る舞わせてくれ。それに合う飲み物もピッタリ合わせてみせるよ」
「いいんですか?」
「ああ、もちろん! 宇佐美くんなら大歓迎だよ」
「僕、料理が本当に苦手なんで手料理なんて、実家以外でほとんど食べてなかったんですよ」
「えっ? 彼女は?」
「彼女も料理は苦手だったみたいで……いや、今思えば、僕に作る時間も面倒だったのかも。いつも宅配料理でしたから」
そういうと、さっと大きな身体に包み込まれた。
「わっ!」
「悪い、嫌なことを思い出させたな」
「い、いえ。いいんです。僕もすみません……」
「宇佐美くんのためならなんだって作るから、いつでも言ってくれ」
「はい。ありがとうございます」
そのまましばらく誉さんに抱きしめられたままで、どうしていいのかわからなかったけれど、ゆっくりと誉さんの身体が離れて行った時、少し寂しく感じてしまった。
なんだろう……昨日から、どうも僕は人肌に飢えてしまっているみたいだ。
ロード中
ともだちにシェアしよう!