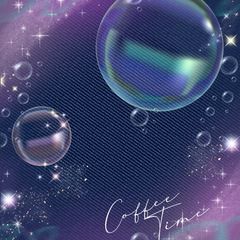2 / 85
俺が、大学生?
『えっ? よろしいんですか?』
慌ただしくも前任の支社長との引き継ぎを終え、ロサンゼルスの生活にも少し慣れてきた頃、取引先の担当者から野球チケットをもらってしまった。
しかも、かなりいい席。
アメリカに来たなら、一度くらいは本場の野球を生で観てみたいと思ってはいたけれど、まさかこんなお宝チケットをもらえるなんて思っても見なかった。
『ああ。娘が突然帰ってくることになってね、空港まで迎えにいくから観られなくなったんだ。よかったら観光がてら、誰か誘って観に行ってくるといいよ。スタジアムの応援は初めてだろう?』
『日本にいたときは何度かドーム観戦はしたことがあるんですが、屋外のスタジアムでの観戦は初めてです』
『なら、きっと楽しめるよ。ピーナッツとポップコーンは忘れないようにな』
パチンとウインクされて、彼は帰って行った。
こんなところがアメリカらしいとでもいうんだろうか。
こんなすごいチケットを貰ってしまって、しかも接待でもない。
ただ純粋に観に行ってくれという話に驚きを隠せないが、せっかくの厚意だ。
無駄にするのも勿体無い。
誘う相手がいないのは勿体無いが、出かけてみるとしよう。
『Oh! Mr.スギヤマ。お出かけですか?』
管理人のジャックが驚いた様子で俺の姿を見ていた。
見慣れない姿が気になるんだろう。
いつもはスーツスタイルの俺も、今日は休日仕様。
と言っても野球観戦だから、白Tシャツに黒の七分袖パーカー、ベージュのチノパンでカジュアルに決めてみた。
前髪を下ろしているから、いつもの印象とはちょっと違うように見えるかもしれない。
しかも、ここに来てからというもの慣れない環境と仕事に忙殺されて、近所のスーパーに買い物に行くくらいしか出掛けていなかったから、ジャックが驚くのも無理はない。
『ジャック、そうなんだ。実はすごいチケットを貰ってね』
社宅として住んでいるこのアパートの管理人をしているジャックに、頂き物のチケットを見せると
『わぉっ! これはすごいチケットですね!』
と目を輝かせていた。
『スタジアムで観るのも初めてだし、楽しみなんだよ』
『スタジアムの凄さに驚きますよ。ぜひ楽しんできてください。車を用意しますね』
『いや、今日はいいよ。仕事で行くわけじゃないし、久しぶりにバスや電車に乗ってみたいんだ』
『ですが、慣れないと危ないですよ』
『ロサンゼルスは大学時代にも住んでいたし、少し土地勘もあるから問題ないよ。何かあったら、連絡するから』
『そうですか? わかりました。どうぞお気をつけて』
ここにきてわかったが、ジャックはかなりの心配性だ。
日本支社からの赴任者をこの社宅で預かっているのだから当然といえば当然なのかもしれないが、そこまで心配されると不安になるな。
そんなに俺は危なっかしく見えるのだろうか?
ちょっと心配になりながら、バスと電車を乗り継ぎ危なげなくスタジアムのある街に到着した。
なんだ、心配することなかったな。
そんなふうに気を緩めたのが悪かったのか、突然逞しい身体をした白人の男二人が俺の前に立ちはだかって、声をかけてきた。
『やぁ、可愛い子猫ちゃん。これからどこに行くんだ?』
子猫ちゃんって……。
もしかしてこれってナンパ?
『悪いけど、俺……男だよ。ナンパするなら、他の人当たってくれる?』
『男なんて、そんなのわかってるよ。君が可愛いから声かけたんだ。惹かれるのに男とか女とか関係ないだろう?』
『えっ?』
まさか、男が男に普通にナンパしてくるなんて思いもしなかった。
こんなところで日本じゃないことを痛感するなんてな。
今まで日本じゃありえなかったことに驚いている間に、あっちは了承だと思ったのか、
『じゃあ、どこ行く?』
と腕を取られてしまった。
『悪いが付き合うつもりはない。離してくれ!』
『またまた。そんな嫌がったふりしたって喜んでるのはわかるんだぜ。俺たち二人でいっぱい可愛がってやるから、安心してついてきなよ。こんなかわい子ちゃんゲットできるなんて、今日はツイてたな』
『ほんと、ほんと。今日は俺からさせろよ』
『何言ってるんだ、俺が見つけたんだぞ』
『ちょっと離してって!!』
男たちが盛り上がっている中、必死に声をかけ手を離してもらおうとしているけれど、逞しい男の腕力に非力な俺の力が敵うはずもなく、ぐいぐいと引っ張られていく。
『本当に、ちょっと待ってって!!』
必死に大声を上げた瞬間、ふっと自分に影がかかったかと思うと、俺と男たちの間に割り込む男の姿が見えた。
『ちょっと、この子俺の連れなんだけど、勝手にどこに連れて行こうとしてるわけ?』
『はぁ? なんだ、お前』
『聞こえなかったのか? この子の連れなんだけど。いい加減手を離してくれないか?』
『くっ――! なんて力だっ! おいっ、わかったから手を離せよ』
俺の手から男の手が離れたのを確認して、彼は男たちの腕から手を離した。
『連れなら、そんな可愛いの一人で歩かせるなよっ!』
男たちは捨て台詞を残して足早に立ち去っていった。
『あ、あの……ありがとうございます』
「ふふっ。君、日本人だろう? 大学の留学生かな? 君みたいな可愛い子が一人で歩いていたら危ないよ」
「はっ? えっ? いや、日本人、だけど……大学生って………私は30歳だけど……。絶対君の方が年下だよね?」
「はっ? 30歳? うそっ! まさかっ!」
目を丸くして驚く彼の姿に、俺の方が驚きを隠せない。
確かに日本人は童顔だって言われるし、俺もこっちにきてからかなり若く見られるけど、まさか同じ日本人の彼にまで勘違いされるとは思わなかった。
もしかしたら、今日はスタジアムに行くからラフな格好をしてきたからいつもより若く見えてしまったのかもしれない。
「本当だって。先月30歳になったところだし」
そう、実は宏樹と最後に会ったあの日は俺の誕生日だった。
だからこそ、家に呼んでくれたと思っていたのに、誕生日プレゼント代わりにあんな話をされるとは思ってもなかった。
って、もういい加減にあいつのことを思い出すのはやめよう。
「すみません、てっきりこの辺の大学に留学できている大学生だとばかり……」
「いや、助けてくれたんだから別に気にしていないよ。童顔なのはわかっているしね。ああ、今日は前髪を下ろしていたから勘違いさせてしまったのかも。ほら、こうすれば大学生には見えないだろう?」
「――っ!!!」
いつものように前髪をあげて見せると、彼はさらに目を丸くしてその場に立ち尽くしていた。
ロード中
ロード中
ともだちにシェアしよう!