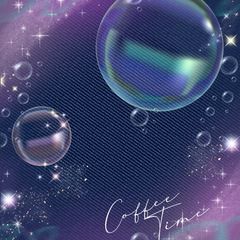14 / 85
一直線になれるほど……
「さて、まずは大智さん。これ、付けてください」
そう言って手渡されたのは、紺色のエプロン。
紐の部分は白でなんとなくオシャレな感じがする。
「ありがとう。これ、透也くんの?」
「はい。私はもう一枚あるんで大丈夫ですよ」
さっと黒のエプロンを見せてくれる。
これも紐は白でどうやら色違いのお揃いらしい。
「これって、もしかして彼女、のとか……?」
「えっ?」
「あっ、いや。ごめん、余計なこと聞いたな」
そんなの愚問だったな。
透也くんくらいイケメンで、甲斐甲斐しく尽くしてくれるような男なら、周りの女性が放っておくわけない。
短期出張だし、流石にここには連れて来れなかっただけだろう。
きっと今頃、彼女は心配だろうな。
透也くんが浮気するような不誠実な人には見えないけれど、離れていると不安になるものだ。
俺は同じ日本にいたって、いつも不安だった。
宏樹が電話の最後に言ってくれる愛しているという言葉だけを拠り所にしていたんだから。
でも……
――あんなのただの挨拶みたいなもんだろ。嘘だろ? ずっと真に受けてたわけ?
あの時、鼻で笑った宏樹の顔を今でも忘れられない。
透也くんは絶対にそんなことは言わないだろうけど……。
「いえ、気にしないでください。言っときますけど、恋人は社会人になってからはいませんよ。大学の時にほんの少し付き合った相手はいますけど、1ヶ月くらいでフラれてるんで。そこからはいないですね」
「えっ? 透也くんがフラれる? フるんじゃなくて?」
「大智さん、酷いですよ。どんなイメージ持ってるんですか?」
「あ、いや。悪い。ただ透也くんがフラれる要素なんて全然思いつかないからさ」
「そうですか?」
「ああ。だって、顔は文句なしでイケメンだし、高身長でモデル並みの体型をしてるし、料理は上手だし、さりげなくエスコートしてくれるし、優しいし、一緒にいると心地いいし、それから――」
「ちょ、ちょっと――っ、大智さん! そんなふうに褒められると、照れちゃうんですけど……っ」
「えっ? あっ――!」
思わず透也くんに思っていたことをつい言葉にしてしまった。
男からこんなふうに思われてるなんて、気持ち悪がられるに決まってる。
「いや、あの……変な、意味はないから……っ、あの」
「別にそういう意味でいいんですけどね」
「えっ? 今、なんて?」
「いいえ、なんでもないです。でも、本当にモテないんですよ。好きなものに一直線になっちゃうんで、大学の時は恋人作るより勉強の方が楽しくて、時間があったら図書館行って勉強してたら、ほら、定番のやつですよ。<私と勉強、どっちが大事なの?>って、言われてしまいまして……正直に勉強だって答えたら、その場でフラれました。ははっ」
「そんなことが……」
「ええ。だから、それ以来、好きなことだけしてる方がいいかなと思って、一直線になれるほど好きになる人ができないうちは恋人作るのはやめようって思ったんですよ」
「一直線になれるほど……好きになる人……」
そうか……。
確かに俺にとって、宏樹はそこまでの相手じゃなかったな。
いつも機嫌を窺って無理してた気がする。
毎日会いたいと思えるほど、好きになった相手ならあんなふうにはならなかったのかもしれない。
「そうじゃなきゃずっと一緒になんていられないでしょう?」
「ああ、確かにそうだな」
「だから、今すごく楽しいんですよ。好きなことだけしてるので」
「私も、こっちに来てから楽しいな。この生活が合ってるのかもしれないな」
「それって……」
「んっ? どうした?」
「あ、いえ。そろそろ、準備しましょうか」
「ああ。そうだったな。悪い」
透也くんは気にしないでくださいと言いながら、冷蔵庫から次々に野菜を取り出していった。
白菜、春菊、長ネギ、きのこ、焼き豆腐……この充実のラインナップを見ていると、ここがアメリカだということを忘れてしまいそうだ。
「じゃあ、大智さん。白菜を切るのをお願いしていいですか?」
「ああ。どう切ればいい?」
そう尋ねると、透也くんは俺を後ろから抱きしめるように覆い被さって、俺の握っている包丁の手の上にそっと乗せた。
「これくらいの大きさで、あとは適当にトントン切ってくれたらいいですよ」
「――っ、あ、ああ。わかった」
抱きしめられながら、耳元で囁かれるとドキドキしてしまう。
この早い鼓動がなんとか気づかれなければいい。
今の俺の頭にはそのことしか考えられなかった。
ロード中
ロード中
ともだちにシェアしよう!