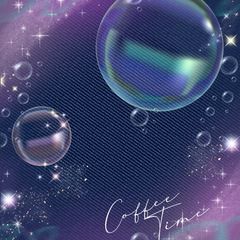15 / 85
冗談だったんだけど……
「大智さん、上手ですね。もう野菜全部切り終わってるじゃないですか」
「意外と楽しくって」
「そんなふうに思えたら十分ですよ。大智さん、こっちもやってみますか?」
透也くんがやっているのはあのミートスライサーとやらで、大きなステーキのような肉を薄切りにしている。
その姿はまるで肉職人のようだ。
「いや、それはちょっと技術がいりそうだから見ておくよ。でも、この肉……サシが入ってすごく美味しそうだな」
「ええ。アメリカの肉は結構赤みが多いんですけど、あのスーパーはサシの入った肉が充実してるんですよね。肉を買うならあそこがおすすめですよ」
「そういえば、ステーキ肉も多かったな。美味しそうだった」
「ふふっ。じゃあ、今度はステーキもしましょうか。結構ステーキ焼くのも得意なんですよ」
そんなことを話しながらもすき焼き用の薄切り肉はどんどん出来上がっていく。
「本当に職人技だな」
「ふふっ。今日は大智さんの前なので気合い入れましたよ。喜んでもらえて何よりです。さぁ、これで終わりです」
山盛りになった肉をテーブルに置き、手際よく次の準備に取り掛かる。
すき焼き用の鍋に透也くんの手作りの割下を入れ、さっき薄切りにしたばかりの肉を入れていく。
「うわっ! 美味しそうっ!」
「ふふっ。味見してみますか?」
「味見?」
「はい、あーん」
そう言ってたった今、割下に入れて美味しそうな色に変わった肉を俺の口の前に持ってくる。
これって味見っていうんだろうか?
でも、目の前で甘辛な割下のいい匂いをさせている肉を拒む理由なんてない。
理性よりも本能が先に出てしまい、あーんと口を開けると、透也くんが嬉しそうな表情をしながら口に入れてくれた。
「んんっ! はふっ、おいひぃ」
「ふふっ。よかったです」
俺の言葉をお世辞だと思っているのか、笑顔でさらっと流しているようだけど、本当にびっくりするくらい美味しい!
いや、本当に。
すき焼き専門店で食べてるんじゃないかと思うくらい、味がしっかりしている。
多分俺が今まで食べてきたすき焼きの中でもダントツ美味しい。
「いや、本当に美味しいよ。こんなすごいのが家で食べられるなんて幸せだな」
「大智さんにそんなに褒められると調子に乗ってしまいますよ」
「いや、ほんとだって! 朝食も美味しかったし、こんなすごいのが毎食食べられるなら、すぐにでも奥さんにしたいくらいだよ」
いつもならこんな冗談なんて言ったりしない。
でもそれくらい本気で美味しかったんだって言いたかったんだ。
ノリのいい透也くんのことだから、きっと
――またまたぁーっ、大智さんもそんな冗談いうんですね。でも嬉しいです。
くらいのことなら返してくれるだろうと思ってた。
でも……
「いいですよ。大智さんが奥さんにもらってくれるなら、喜んで」
と笑顔のままでとんでもない言葉が返ってきた。
「えっ――!? と、透也くん……?」
「ふふっ。どうしたんですか?」
「いや、だって……っ、今……」
「大智さんが奥さんにしたいって言ってくれたので、喜んでと返したんですけど間違ってました?」
「いや、だって……」
同じ言葉しか返せないくらい、頭の中がテンパってる。
これは本気なのか?
それとも冗談?
常識的に考えたら冗談に決まってるけど、でも……真面目な透也くんのことだからもしかしてってことも……あったり、いやいや、するはずない。
少し冷静になろうと思っていたのに、さっきまで笑顔だった透也くんの表情がみるみるうちに悲しげになってくる。
「もしかして……冗談でした? やっぱり……私のご飯、美味しくなかったですか?」
「い、いや! 美味しいよっ! 本当に美味しいっ! 奥さんにしたいって言ったのも本気だからっ!」
「じゃあ、決まりですね。私は今日から大智さんの奥さんです。男に二言はないですよね?」
さっきまでの悲しげな顔が一転、満面の笑みで笑みで返されてしまった。
その勢いに押されるように気付けば、
「えっ? あ、ああ……」
と返してしまっていた。
「ふふっ。じゃあ、大智さん。すき焼き始めましょうか」
そういうと、さっきのことなんか忘れたように手際よくすき焼きを作り始めた。
甘辛い美味しい匂いが漂ってきたけれど、俺の頭の中はさっきの奥さん事件のことでいっぱいでただ茫然と透也くんがすき焼きを作るのを見つめるしかできなかった。
「できましたよ」
俺がぼーっとしている間にすき焼きが完成して、どうぞと生卵が溶かれた器を渡される。
「あ、ありがとう」
「ふふっ。奥さんとして当然のことですよ」
「――っ!!」
その後も次々とすき焼きを装ってくれたり、甲斐甲斐しい世話になぜか心地よさを感じてしまい、食事を終える頃には食後のお茶までなんの違和感もなくもらってしまっていた。
ロード中
ロード中
ともだちにシェアしよう!