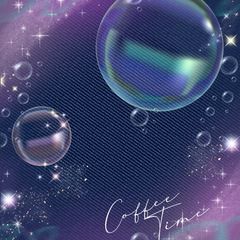26 / 85
心の声を隠せない
「大智さん、こっちです」
連れて行かれた部屋は他の半個室の部屋と違って、完全個室。
「ここならゆっくり話せますよ」
「透也くん……」
にっこりと笑顔を向けられてホッとする。
俺が席に着くと、透也くんは椅子を動かして、俺にピッタリと寄り添うように座った。
「あ、あの……」
「すみません、大智さん。今だけ、隣に居させてください」
「今だけ? ずっと、居てくれないのか?」
「――っ、大智さんが望んでくれるなら喜んでずっと隣に居ますよ!」
ギュッと抱きしめられてホッとする。
透也くんの身体に触れ合う右側が心地いい。
ああ、もう本当に離れられなくなっちゃったな。
「俺……もう、恋をしないって……そう、決めてたんだ」
「前にそう言ってましたね。だから、俺が全部忘れさせるって――」
「早く忘れたいんだ。だから……今夜にでも聞いてくれるか?」
「はい。大智さんのことならなんでも教えてください」
本当はすぐにでも話したかった。
でも、そうしたらお兄さんの料理を楽しめない気がした。
「嫌いに、ならないかな?」
不安はそれだけ。
「大智さん。俺が大智さんを嫌いになることなんて、永遠にありえません」
永遠なんて……それこそ、ありえない。
今までの俺ならそう言ったかもしれない。
でも……透也くんなら、信じられた。
だから、ずっと心にしまっていた傷を話したいと思ったんだ。
「透也くん……好きだ」
「――っ、大智さんっ!!」
溢れてしまった思いが思わず口をついて出た。
「ああ……っ、もうこのまま家に連れて帰りたいです」
さらにギュッと抱きしめられるのがたまらなく嬉しい。
「夕方も……迎えに来てくれるんだろう?」
「はい。もちろんです」
「あ、でも……」
また透也くんをみられるのが嫌だな……。
あ、そういえば、なんでそう思ったのか教えてくれるって言ってたっけ。
あれ、どういう意味だったんだろう……。
「ふふっ。大智さん。心の声が漏れてますよ」
「えっ? 今の?」
「はい。全部聞こえてましたよ」
「――っ、聞こえてたなら、教えてくれ。さっきのどういう意味だったんだ?」
「ふふっ。大智さん、嫉妬したんですよ」
「し、っと?」
「はい。俺のウィンクを誰にも見せたくない、とか……俺の名前を知られたくない、とか……それって、嫉妬以外にないでしょう?」
「あ――っ」
うそ――っ、俺が……嫉妬?
でも……そう、なのかも。
全部を俺だけのものにしたいって思ってた……。
うわ……っ、恥ずかしい……。
「恥ずかしくなんかないですよ」
「えっ? 今……」
「ふふっ。大智さん、テンパリすぎると心の声が漏れちゃうんですね」
「うそっ、今のも聞こえてた?」
「はい。大智さんの本心が聞けて俺は嬉しいですけど、他の人にはダメですよ。俺も嫉妬しちゃいますから。心の声は俺だけに聞かせてください」
「透也くん……」
こんなふうに心の声が漏れるなんて、今まで一度もなかった。
そんなにまで動揺することもなかったし。
「大智さん……」
あ、キスされる……。
それがすごく嬉しくて、俺はそっと目を瞑った。
ゆっくりと顔が近づいてきたその瞬間、突然扉が叩かれた。
ビクッと身体を震わせると、
「はぁーーっ、なんてタイミングだ」
と透也くんががっかりと項垂れていた。
そんな俺たちの様子を知るはずもないお兄さんが
「お待たせ」
と料理を運んできてくれた。
透也くんはお兄さんに何かいいたげだったけれど、俺は運ばれてきた料理にすでに目を奪われていた。
「わっ! これ……」
「こっちじゃ滅多に食べられないよ、これ、天然だから」
「えっ! すごーいっ!! ありがとうございます!!」
「ふふっ。いい反応してくれるなぁ。じゃあ、どうぞごゆっくり」
目の前にあるのは、美味しそうに脂の乗った鰻。
このタレの匂いだけでご飯が何倍も食べられそう。
「身内の店なんで、あんまり褒めすぎるのもアレですけど、アメリカでここまでの鰻料理を出す店はないですよ」
「いや、本当に。まさかこっちで鰻を食べられるなんて思ってなかったよ」
「よかった。大智さん、和食が好きだからきっと鰻も好きだろうと思ったんですよね。じゃあ、食べましょうか」
「いただきます!!」
ついさっきまで愛の言葉を言い合い、キス寸前までしていたとは思えないほど、俺はもう鰻に夢中になっていた。
そんな俺をみて、透也くんが嬉しそうに笑っていたことには俺は全く気づいていなかった。
「ふぅー、お腹いっぱい!」
「ふふっ。完食でしたね」
「ああ、こんなに美味しい鰻、日本でも食べたことないから夢中になっちゃったよ」
「兄貴が聞いたら喜びますよ。じゃあ、そろそろ行きましょうか」
「あ、俺が出すよ」
「ああ、大丈夫です。もう支払いは済ませてるんで」
「えっ、でもそれじゃあ……」
「身内の店で、大智さんからお金取るなんてそんなことできませんよ」
「でも……俺も身内になるんだろう?」
「えっ……それって……」
「あっ!」
もしかして、自意識過剰だった?
お兄さんに紹介されただけで身内なんて図々しかった?
「わっ!」
「もう! どれだけ俺を喜ばせるんですか! 自意識過剰なんかじゃないですよ! 身内だって思ってもらえて、俺……すみません。もう我慢できません」
「んんっ!!」
急に抱きしめられたと思ったら、真っ赤な顔で怒られて、そのままキスされた。
一気にいろんなことが押し寄せてきて、俺のキャパシティをオーバーしそうだけど、それでも俺が思ったのは、やっとキスできた……の一言。
透也くんとの甘くて蕩けるような優しいキスに、俺はすっかり身を任せてしまっていた。
ロード中
ロード中
ともだちにシェアしよう!