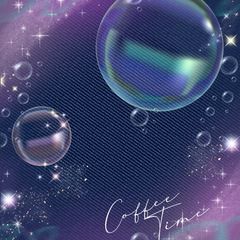27 / 85
距離が近くなる
「ご馳走さまでした。本当に美味しかったです」
「気に入ってもらえて嬉しいよ。うちは鰻以外にも和食ならほとんど出しているから、いつでも食べに来て」
「いいんですか?」
「ああ、杉山さんなら大歓迎だよ」
「わぁ、ありがとうございます」
男同士の恋愛なんてずっと隠さないといけないと思っていたのに、俺たちが付き合っているとわかっても態度が変わらないどころか、こんなにも歓待してくれるなんて思いもしなかった。
本当にお兄さんって優しい人だな。
透也くんとはまた違う安心感がある。
「大智さん、あんまりそんなに可愛い顔を兄貴に見せないでください」
「えっ? 可愛いって……っ。そんなの思うの、透也くんだけだろう」
「そんなことないです! 大智さん、本当に可愛いんですよ」
「――っ、ほ、ほら、そんなことばっかり言ってないで、そろそろ行かないと!」
「ああ、そうでした」
慌てて話題を変えると、透也くんは時計を見てからお兄さんに視線を向けた。
「兄貴、今日はありがとう。あのさ、一つ言い忘れてたんだけど……」
「なんだ?」
「その、大智さん……兄貴とタメだよ」
「はっ?」
「えっ?」
タメ、って……同じ年、ってことだっけ?
はぁ? うそっ!
いや、絶対俺より2、3個は上だと思ってた。
そう思ったのはきっと俺だけじゃなかったみたいだ。
お兄さんがすごくびっくりした顔で俺をみてる。
鳩が豆鉄砲食ったような顔ってこういうのをいうんだろうな。
「それ……本当、なのか?」
「大智さん、先月30歳になったって言ってましたよね?」
「あ、ああ。そう、だけど……」
「じゃあ、実質兄貴の方が下だな。兄貴は来月30になるんだから」
そうなんだ……って、か二ヶ月くらいなら上も下もないけど。
「マジか……。正直言って、透也と同じか下だと思ってた……杉山さん、すみません」
「いいえ。そんなっ! 結局同級生なんですし、今まで通り敬語なしで大丈夫です」
「あの、じゃあ杉山さんも気楽に話して。その方が話しやすい」
「えっ、いい、のかな……?」
「ああ、そっちの方がいいな。じゃあ、苗字じゃなくて名前でもいい?」
「はい、いいで――」
「ダメだ! 大智さんを名前で呼んでいいのは俺だけなんだよ」
俺の言葉を遮るように透也くんがお兄さんに声を張り上げた。
どうやら自分と同じ呼び方になるのが気に入らないみたいだ。
ふふっ。
なんかこういうところは弟っぽい。
「じゃあ、透也くんは呼び捨てで呼んでくれたら良い。そうしたらお兄さんとは同じにはならないだろう?」
「えっ? 良いんですか?」
「ああ、その代わり俺も透也って呼んでいい?」
「――っ!! はいっ! もちろんです」
「ふふっ」
さっきまで拗ねていたくせに、もう嬉しそうに笑ってる。
本当におっきなワンコみたいだ。
「透也、大智さんを呼び捨てにできるようになったのは、俺のおかげだって忘れるなよ」
「うるさいよ、兄貴は」
「ははっ。大智さん、本当ワガママで典型的な弟なやつだけど、これからもよろしく頼む。あ、俺のことも祥也で良いよ」
「あ、はい。祥也さん、あの……透也、は……その、いつも優しいし、俺のことばかり優先して心配になるくらいだよ」
「えっ? 透也が優しくて、優先する? マジか、信じられないな」
驚いた顔で透也を見る。
その顔の方が俺はびっくりだ。
「言ったろ? 俺、本気なんだよ」
「そうか……よかったな」
二人が意味深に顔を見合わせて笑っているのを俺はただ見つめるしかなかった。
「大智、行きましょうか」
「えっ、あ、ああ。お兄さん、ご馳走さまでした」
もう一度お兄さんに声をかけて店を出た。
俺の手をとってスタスタと歩いていく透也の後ろをついていく。
まるで来た時と逆みたいだ。
それにしても初めて呼び捨てで呼ばれた時……なんだかすごくドキッとした。
でも呼び捨て、悪くないな。
むしろ嬉しい。
「透也? 何か怒ってる?」
「えっ? いえ、違いますよ。なんだかちょっと照れ臭くて……」
「そうか、ならよかった。今日は驚いたけど、お兄さんに紹介してもらえて嬉しかったよ」
「日本に帰った時はぜひ両親にも会ってください。もう話はしてるんです」
「えっ? もう? そ、それでなんて言ってた?」
「ものすごく喜んでくれてました。早く大智に会いたいって言ってましたよ。うちの母、大智みたいな息子が欲しいってずっと言ってたんで、俺や兄貴が帰国するより喜びそうですよ」
屈託のない笑顔を見せる透也に、社交辞令なんかは感じなかった。
きっと本当に喜んでくれているんだろう。
ああ、俺は幸せ者だな。
透也と出会って、一生分の運を使い果たしたのかもしれない。
支社まで送ってもらって、セキュリティーゲートの中に入るまで見送ると透也は自分の会社へ戻って行った。
今までずっと一緒だったくせに、離れてからほんの数分しか経っていないのにもう会いたくなる。
もうすっかり一緒にいるのが普通になってきたな。
本当に透也が帰国した後、生きていける気がしない。
心の中でため息をついていると、
「支社長。例のプロジェクトの件、うまく行きそうなんですけど、相手先が発案者と直接話して、できればその人を今回のプロジェクトのリーダーに据えて欲しいと仰ってるんですけど、本社からこっちにきてもらえないですか?」
と部下の子が相談に来た。
「このプロジェクトの発案者は……ああ、宇佐美くんか。そうだな彼に来てもらえればスムーズにことが進むだろうな。わかった。とりあえず本社に話を通してみるよ。うちに来てくれるのが一番だが、あの子はかなりのやり手だからね。本社の方が手放すかどうか……。まぁ何とか掛け合ってみよう。こっちのプロジェクトの成功がかかってるからな」
「はい。支社長、お願いします!」
宇佐美くんか……。
あの子がこのままこっちの支社にいてくれたら、俺の赴任期間も短くなるかもしれないな。
って、いくら早く透也と日本に戻りたいからってそんなこと考えたらダメか。
自分の話は置いといて、とりあえず、本社に連絡しておこう。
ロード中
ともだちにシェアしよう!