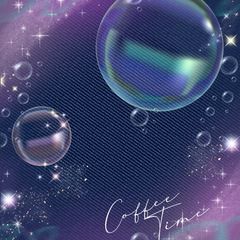24 / 33
僕にも甘えてほしい
「――っ! ああ、もうっ本当に無防備すぎるな」
「えっ? いま、なんて……?」
なぜか苦しげに顔を背けていたのが気になって尋ねたけれど、
「あ、いや。なんでもない。宇佐美くん、シャワーを浴びてくるといいよ。拭っただけじゃベタベタするだろう?」
と言われて、一気に我に返った。
恥ずかしい。
さっさと身体を清めてこよう。
「――っ、は、はい。すみませ――わっ!!」
「ふふっ。気をつけて。転ぶと危ないよ」
急いでベッドから下りようとしたけれど、壁側にいたから誉さんを跨ぐのが大変で足を引っ掛けそうになってしまった。
誉さんがすぐに抱きしめて、そのままベッドから下ろしてくれた。
「ありがとうございます」
誉さんににこやかな笑顔で見送られながら、僕は急いでお風呂場に向かった。
少し湿っている下着とパジャマを脱ぎ洗濯機に放り込み、浴室に入った。
夜はゆったりお湯に浸かりたいけれど、朝はシャワーだけでスッキリだ。
特に昨日は熟睡しているし、さっき誉さんに久々のアレを出してもらったからなんだか身体も軽い気がする。
ボディーソープで今はすっかり元の大きさに戻ってしまったモノを洗いながら、ふと思う。
誉さんにしてもらえて気持ちよかったけど……昂った時でさえ誉さんの手にすっぽり入るって……今まで誰とも比べたことなんてなかったからわからなかったけれど、僕のって小さい方なんだろうか?
身体の大きさと比べたら平均じゃないかと思うけど、どうなんだろう……。
もし、すっごく小さいんだったらそんなのを誉さんに触られてしまったという恥ずかしさと、誉さんのはどれくらいの大きさなんだろうという興味が湧き上がってくる。
見せてくださいって頼んだら、見せてくれるんだろうか……。
というか、
――若い成人男性なんだし、朝起きた時はそうなるのが普通なんだ
って言ってたんだから、もしかしてあのとき誉さんもおんなじ状態だったんじゃ?
だったら、僕だけじゃなくて誉さんだって手伝ってあげた方が良かったんじゃない?
それなのに僕は……。
自分だけスッキリして、誉さんに気遣うこともせずにさっさとシャワー浴びたりして……。
考えてみたら僕、すごくひどい奴じゃない?
ああ、もう!
なんでそのことに気づかなかったんだろう。
もしかしたら誉さん、僕がいなくなった後で自分で処理してたのかも……。
ああ、もう本当に僕バカだ!
自分だけあんなに気持ちよくしてもらったくせに。
甘えていいって言われたからって甘え過ぎだろう。
これはよくない!
絶対によくない!
ちゃんと話さなきゃ!!
僕は急いで浴室から出て、身体を拭いたタオルを洗濯機に放り込みスイッチを押した。
ここに備え付けの洗濯機はかなり優秀で洗剤自動投入機能がついているからこういう時は楽でいい。
脱衣所に置いてあるTシャツと短パンを穿いて勢いのままにお風呂場を出ると、キッチンからいい匂いが漂ってきた。
「あっ、朝、ご飯……」
「早かったな。もう出てきたのか?」
「は、はい。あの僕……」
「どうした? もうすぐできるから、ゆっくりしてていよ」
着心地の良さそうな白のカットソーと濃いネイビーのスラックスを爽やかに着こなした誉さんににっこりと微笑まれて、さっきまでの勢いが一気に削がれてしまった。
どうしていいかわからず、キッチンが見えるダイニングテーブルの椅子に座り、誉さんが料理をしているところを見つめる。
けれど、さっきまであのことばかり考えていたからか、自然と誉さんの股間ばかりに目がいってしまう。
ゆったりとしたスラックスだからか、誉さんの形状も大きさもわからない。
もう処理してしまったんだろうか?
それとも今日はそんな状態になってなかった?
さっき抱きしめられていた時はすぐそばにいたからわかったはずなのに、あの時は自分のことに夢中で全然わからなかった。
あの時、今度は誉さんも……って言えていたら、よかったのに。
ああーっ。
自分の不甲斐なさに頭を抱えていると、
「……みくん? 宇佐美くん?」
と頭上から声が聞こえ、慌てて顔を上げた。
「――っ、あっ、ごめんなさいっ!」
「いや、謝ることは何もないが、どうしたんだ? 風呂から出てきて少し様子がおかしいな」
「そんなことは……」
「いや、何かあったんだろう? 何事も隠さずに教えてくれないか?」
そういうと、誉さんは僕の向かいに腰を下ろした。
「どうしたんだ? もしかしてさっきのことが嫌だったのか?」
「えっ? さっきのこと?」
「ああ、私が君のを……その、してあげたことだよ。気持ち悪くなった?」
「いえ! そんなことは全然! むしろ、僕の方が――」
「えっ? どういうことだ?」
誉さんの真剣な目で見つめられ、どうしようかと思ったけれどここで何も言わないわけにはいかない。
「あ、あの……僕……酷いことしちゃったなって……」
「酷いこと? 宇佐美くんが?」
「はい。だって、誉さん言ってたじゃないですか。若い成人男性なら朝起きた時そうなって当然だって」
「あ、ああ。言ったな。それがどうかしたか?」
「だったら誉さんもそうなってたんじゃないかって……ですよね?」
「えっ? あ、ああ。まぁ、そう、かな……」
言いづらそうにしているのはきっと僕のことを気遣ってくれたんだろう。
「僕、それも知らずにさっさと自分だけシャワーに行って申し訳なかったなって……そう思ってたんです」
「そんなこと気にする必要はないよ」
「でも……僕だって、誉さんを気持ちよくしてあげたかったです」
「――っ!!! それって――」
「だって、自分でするより人にしてもらった方が断然気持ちいいですもんね」
「えっ? あ、ああ。そうだな」
「だから、次は僕にもさせてください!」
そう頼むと誉さんは目を丸くして驚いた。
「え――っ!! それは……」
「だめ、ですか?」
「い、いや。だめ、ではないが……本当にいいのか?」
「はい。僕だって、誉さんに甘えて欲しいです」
「くっ――! わかった。じゃあ、お願いします」
「ふふっ。はい、任せてください!」
僕は誉さんに甘えてもらえたことが嬉しくてたまらなかった。
ともだちにシェアしよう!