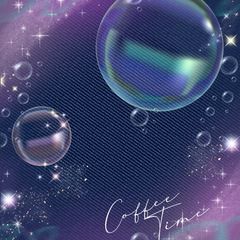23 / 33
どうしてこんな時に
「んっ……わっ!」
目を覚ますと、目の前に誉さんの顔が見えて思わず声をあげてしまった。
起こしてしまう! と慌てて口を押さえたけれど、誉さんはまだ寝ているようだ。
そういえば、一緒に眠ったんだっけ。
あまりにも熟睡してて忘れてた。
夢も見ないほどぐっすり眠ったのっていつ以来だろう。
抱きぐるみと間違われてそのまま眠っちゃったけど、僕の方に抱きぐるみの効果があったみたいだ。
頭がすごくスッキリしてる。
それはすごくよかったんだけど……。
この状態をどうしよう。
誉さんにギュッと抱きしめられたままで身動き一つ取れないし、かといって、無理やり動いてせっかく寝ている誉さんを起こしたくない。
とりあえず腕を外そう。
僕の身体にまわっている誉さんの腕をゆっくりと外そうとしていると、
「うーん」
と声をあげ、今よりさらに抱き込まれてしまう。
誉さんの胸に顔が押し付けられて、誉さんの匂いに包まれるとなんだか不思議な気持ちになる。
寝る時よりもずっと強く誉さんの匂いを感じているうちに、自分に異変を感じてしまった。
え――っ、なんで?
アメリカに行く前だって、こっちにきてからだってそんなことしばらくなかったのに……っ。
自分でも信じられなくて、そっと布団の中に腕を入れ確かめてみたけれど、やっぱり勃ってる。
なんで? 嘘だろっ?
何もしてなかったから、溜まってるとか?
そうだとしてもなんでこんな時に……。
誉さんに気づかれたら絶対嫌われる!
もう一緒には寝てくれないかもしれない。
いや、それどころかここに泊まるのが嫌になって出ていっちゃうかも。
ああ、もうなんでだよっ。
いつもこんなこと全然なかったくせに、どうしてよりにもよってこんな時に……。
どうやったら治まるんだっけ?
それすらもわからなくなるほどテンパったまま、誉さんの腕の中でなんとか鎮まってくれるのを待つけれど、焦れば焦るほど僕の期待に反してさらに硬さを増してきてしまう。
どうしよう、どうしようと焦るあまり、足をもぞもぞさせていると
「んっ、宇佐美くん……おはよう」
と誉さんが目を覚ましてしまった。
こんなの誉さんにバレちゃいけない。
必死に冷静を装いながら、
「お、おはようございます」
と挨拶したものの、不思議そうな顔で見つめられてしまった。
「ほ、誉さん、どうかしましたか?」
「いや、宇佐美くん……やけにほっぺたが赤いね。熱でもある?」
「えっ? い、いえっ。熱なんてそんな……っ」
これ以上近づかれたら気付かれるかもと思うけれど、誉さんは僕を抱く力を強めながらおでこを合わせてくる。
「うーん、熱はなさそうだけど……んっ?」
「――っ!」
気付かれたっ!
そう思った瞬間、さらに顔が熱くなっていくのがわかる。
「なるほど。そういうことか……」
「あ、あのっ、べ、弁解させてくださいっ。僕、本当にこんなこと全然なくてっ。こんななっちゃったのも覚えてないくらい久しぶりなんです。だから、あのっ――」
「気にしなくていいよ」
「えっ?」
「宇佐美くんはまだ若い成人男性なんだし、朝起きた時はそうなるのが普通なんだ。今までが異常だったんだよ」
「い、じょう……?」
「ああ。ハードな仕事だったり、ストレスだったり、悩みだったりがあって身体に異常をきたしていたから、そこまで身体が追いついてなかったんだ。こんな状態になれたってことは、宇佐美くんが全てから解放されてリラックスできてるってことなんだよ。だから、恥ずかしがることなんて何もないんだ。私と一緒に寝たことで宇佐美くんがリラックスできたなら、嬉しいくらいだよ」
「そう、なんですね……」
こんなの誉さんに知られたら絶対に嫌われるって思ってた。
でも、嫌われるどころかこんなにも優しい言葉をかけてくれるなんて……。
「久しぶりでそんなになってたら辛いだろ? 早く鎮めてあげたほうがいいんじゃないか?」
「あ、はい。そうなんですけど……なんか、もう久しぶりすぎてどうやって治めてたかもわからなくなってて……」
「――っ、そ、そうか。ならもっとリラックスさせてあげようか?」
「えっ? それって、どういう意味ですか?」
「宇佐美くんは横になって目を瞑っていたらいい」
「えっ、な――っ、ああっ! そ、んなとこ……っ」
誉さんが言っていることがわからなくて戸惑っている間に、スッと僕のズボンの中に誉さんの手が侵入してきた。
誉さんの大きな手に僕のがすっぽりと包まれて上下に扱かれていく。
「や――っ、ああっ! ほ、まれ、さん……っ、ああっん!」
片手で背中をギュッと抱きしめられて、もう片方の手はさらに激しさを増しながら扱かれる。
上下に擦られながら先端を刺激されているうちに、声を抑えることもできなくてただ本能のままに声をあげてしまっていた。
「そう、何も考えないで気持ち良くなればいい」
「んんっ!!」
耳元で誉さんに囁かれて身体がゾクゾクした瞬間、身体中を激しい快感に貫かれてそのまま僕は出してしまった。
「はぁっ、はぁっ」
ビュルビュルと自分でも驚くくらいの量が出ているのがわかる。
いつ以来かもわからない吐精に途轍もない快感と疲れを感じて息が荒くなる。
「ふふっ。いっぱい出たな。気持ちよかったか?」
恥ずかしくて頷くことしかできない。
ふわっと独特なあの匂いを感じて我に帰った僕は、慌ててベッドの上に置いていたティッシュケースをとり
「すみません。これ、使ってください!」
と数枚のティッシュを差し出した。
「ああ、ありがとう」
誉さんが手を拭いている間に僕も自分のをティッシュで拭い、パジャマを整える。
「あの、本当にすみません」
「謝らないでいいって。私からしたことだ。それよりも宇佐美くんが気持ち良くなってくれてよかった。久しぶりだったんだろう?」
「は、はい。あの、正直……自分で、その……するよりも、断然気持ちよかったです」
「――っ、ふふっ。そうか。ならいつでも任せてくれ」
「えっ、でもそれは……」
「甘えてくれって言ったろう?」
これも甘えることに入るのか?
一瞬そう思ったけれど、久しぶりの快感に頭がふわふわとしていた僕は何も考えることもできず、気づけば、
「お願いします」
と答えてしまっていた。
ともだちにシェアしよう!