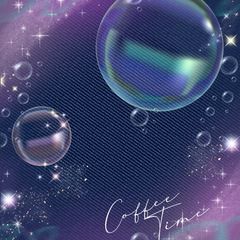26 / 33
非日常の楽しい時間
「ほら、宇佐美くん。口開けて」
「えっ?」
「今日はいい天気だから溶けてしまうよ」
「あ、はい」
言われた通りに口を開けると、スプーンに乗せられたバニラが入ってきた。
シャリっとした食感に甘くて美味しいミルクの味が口いっぱいに広がっていく。
「わぁっ、冷たくて美味しいっ」
「ふふっ。よかった」
「誉さんも食べてください。はい、あーん」
カップに入っていたもう一つのスプーンにバニラを乗せて、誉さんの口の前に持っていくと嬉しそうに口を開けてくれる。
意外とジェラートとか好きなんだな。
ふふっ。可愛い。
「ああ、美味しい、こんな日には最高だな」
その笑顔が眩しくてなぜかドキドキする。
「あっ、僕、ストロベリーも食べてみます」
恥ずかしさを隠すように持っていたスプーンで誉さんが持ってくれているカップのジェラートを掬い取り、口に運んだ。
「あっ!」
誉さんが何か言ったような気がしたけれど、僕は口の中の甘くて美味しいストロベリーに夢中だ。
「んんっ、美味しいっ!」
バニラとはまた違った美味しさにハマってしまいそう。
「あ、誉さんもどうぞ」
持っているスプーンで掬い取って口に運ぶと嬉しそうに口を開けてくれる。
「ああ、本当に美味しいな。バニラよりこっちの方が美味しく感じるよ」
「ふふっ。誉さん……苺が好きなんですね」
「んっ? ああ。そうだな」
なぜか意味深に笑う誉さんを不思議に思いながらも、あーんと差し出されたジェラートを食べながら、僕も誉さんにあげていると
『You’re so lovey-dovey!』
と満面の笑みを浮かべた通りすがりの人たちに次々と声をかけられる。
公園に入ってからはさらにその声は多くなった。
えっ、ラブラブって言われてる?
僕たち、もしかしてカップルと間違われてるとか?
あっ、だからさっきもジェラート屋さんで……
――Have a sweet wee kend!
なんて言われちゃったのかな?
僕とカップルに間違われるなんて……誉さん、嫌だろうな……。
どうしよう……ちょっと気まずい。
そう思っていたのに、
『Thanks.』
誉さんは手を振り、嬉しそうな笑顔を見せながら、声をかけてくれる人たちに気軽に声を返していく。
「誉さん……」
「んっ? どうした?」
「いや、あの……僕たち、カップルに間違われてるみたいで……」
「ああ、そうみたいだな」
「あの、僕なんかちカップルに思われて嫌じゃないんですか?」
「ははっ。そんなのでいちいち訂正したりしないし、仲がいいと思われたくらいだから大したことはないだろう? ここはアメリカだし、同性カップルもたくさん目につくからみんな気軽に声をかけてくれているだけだろうし。それにただ単に私たちが仲がいいと思って褒めてくれている人もいるだろうし、別に嫌な気はしないよ」
確かに。
公園に入ってから、同性も異性もどちらのカップルも普通に目につく。
いや、もしかしたらあの人たちも別にカップルでもなく、ただ仲がいいだけかもしれないしな。
僕が過剰に反応しすぎなのかもしれない。
「そうですね。僕も誉さんと仲良しだと思われたら嬉しいです」
「――っ、そうか。よかった。あ、ジャックが話していた湖が見えてきたぞ」
「ああっ、本当ですね。思ってたより大きな湖でびっくりです! でも、すごく気持ちよさそう!」
「あっちがボート乗り場だな。行ってみよう」
さりげなく手を取られ繋いだまま、ボート乗り場に向かう。
『Hi.二人で乗りたいんだけど、ボートは空いてるかな?』
『ごめんなさい。今ペダルボートが全てで払ってて、手漕ぎボートしかないんだけど大丈夫かしら?』
『ああ、問題ないよ。それで頼む』
『じゃあ、大人二人で二十ドルね』
誉さんがさっと財布を出そうとしたのをみて、僕は手を握った。
「――っ、宇佐美くん。どうした?」
「さっきジェラートご馳走になったので、ここは僕が出します」
「いや、いいよ。私が散歩に誘ったんだから、出させてくれ」
「でも……」
「いいから。甘えてくれって言ったろう?」
「あっ…」
そうだった。
誉さんは僕の反応に笑顔を見せるとさっと財布から二十ドル出して支払ってくれた。
「ありがとうございます」
「ああ。じゃあ、行こう」
スタッフさんに案内されて、手漕ぎボートにまず誉さんが乗り込んだ。
そして手を差し出して僕の手を握り、ボートに乗せてくれた。
「わっ!」
初めて乗る不安定なボートの上でびっくりして抱きついてしまったけれど、さすが誉さん。
体幹が鍛えられているようで、僕が抱きついたくらいじゃ微動だにしなかった。
「大丈夫か?」
「は、はい」
「じゃあ。宇佐美くんはこっちに座って」
言われた通り、進行方向に背を向けた誉さんの向かいに座ると、誉さんは器用にオールを漕ぎ出した。
ボートはまるで氷の上を滑るようにスイスイと進んでいく。
「誉さん、ボート漕ぐの上手なんですね」
「学生時代にボート部の練習に駆り出されたことがあってね。その時はかなり真剣にやっていたからまだ身体が覚えていたみたいだな」
「へぇー、そうなんですか。すごいっ!!」
柔らかな日差しの中、湖の上は心地よい風が通ってすごく気持ちがいい。
アメリカに来てから初めて非日常を味わって、僕は心がスッキリと晴れやかになっていた。
ロード中
ともだちにシェアしよう!