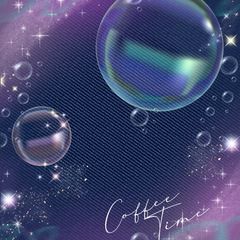27 / 33
硬くて太い
「ここ、来てよかったですね」
「ああ、そうだな。なかなかボートに乗れる機会もないし、ジャックにはあとでお礼をいっておかないとな。どうだ? 宇佐美くんもボートを漕いでみるか?」
「難しそうですけど、できるかな?」
「ふふっ。大丈夫。私が手助けするよ。腰を下ろしたままでいいからゆっくりこっちにおいで」
オールが流れて行かないように止めてから、誉さんは僕の手を取って、ゆっくりと隣に座らせてくれた。
狭いけど、誉さんとくっつくと何故かホッとする。
「両手使っていいから、ゆっくりと漕いでごらん」
誉さんは僕が落ちたりしないように片手で僕の腰をしっかりと抱きしめながら、もう片方の手でオールを漕ぐ。
僕は両手で漕ぐのが精一杯なのに、誉さんの方は片手なのにスイスイ動いてる。
やっぱり腕の筋肉なのかなぁ……。
僕の細っこい腕じゃ難しいんだろうな。
きっと明日筋肉痛になってそう。
でも、自分の力で少しずつ進んでいくボートに嬉しさが込み上げる。
「慣れてくると楽しいですね」
「ふふっ。そう言ってもらえてよかった」
「あの、ちょっといいですか?」
「んっ? どうした?」
誉さんは僕の声に漕ぐのをやめると、すぐに僕のと自分のオールをボートに固定した。
「何かあったか?」
「ちょっと……誉さんの、腕を触ってみたいなって……ダメ、ですか?」
「えっ? 腕を? いや、別に構わないよ……」
「わぁ、本当ですかっ! 嬉しいっ!」
自分で頼んでおきながら少し緊張するけれど、差し出された腕の二の腕にそっと触れる。
「――っ、うわっ! すっごく硬いっ!!」
「くっ――!!」
「それに太いんですね! これくらいが普通ですか?」
「ぐぅ――!!」
「誉さん? どうかしましたか? あっ、痛かったですか?」
「い、いや。なんでもないよ。ボートやってたから人より少し筋肉があるかもしれないが、普通だよ」
えー、これが普通?
そうなると僕の腕はかなり貧相な気がするけど……。
「宇佐美くん?」
「あ、いえ。誉さんのと比べたら僕の腕……すごく貧相だなって」
「貧相って、そんなことはないだろう?」
「いや、そんなことありますって。ほらっ」
カットソーの袖を肩まで捲り上げて見せ、誉さんの腕と比べると半分くらい違う気がする。
しかも僕の腕はぷにぷにしてるし……日に焼けてないから真っ白だし……。
「はぁーっ、やっぱり少しは鍛えないといけないですよねぇ……」
誉さんとあまりにも違い過ぎてため息しか出ない。
でも、誉さんは何故か僕の腕を見たまま動かなくなった。
あっ、もしかして思っていた以上にぷにってたから、驚いてるとか?
そうだよねぇ。
僕もそう思う……。
だって誉さん……こんなに鍛えられた腕が普通だと思ってるんだもんね。
「もうっ! 誉さん、こんな貧相な腕、じっくり見ないでください。恥ずかしいです……」
「あ、ああ。悪い。でも、そんな恥ずかしがるような腕じゃないよ」
「本当ですか?」
「ああ。もちろんだよ。今日ボートを漕いでいつもは使わない筋肉使ってるから、帰ったらマッサージしておこう。ほぐしとかないと筋肉痛になって明日辛いからな」
「はい。じゃあ、僕も誉さんのマッサージしますね」
「あ、ああ。頼むよ」
それからは僕を隣に置いたまま、誉さんが両手でボートを漕ぎ始めた。
僕は誉さんの腕の中に入ったままだ。
誉さんの温もりはもちろん、ボートを漕ぐ時の息遣いや、腕の筋肉の動きまで感じられてなんだかドキドキする。
だけど、さっき向かいに座っていた時より落ち着くし安心する。
なんだかここが定位置という感じでしっくりくる気がする。
なんでだろうと思ったけど、そうか……わかった。
誉さんと一緒に寝ている時と同じなんだ。
僕、ずっと誉さんに守られてるみたいだ。
「うわっ! 危ないっ!!」
突然誉さんが大声をあげ、僕をギュッと抱きしめたかと思ったら、ドォーーンっ! と大きな衝撃が起こり、ボートが激しく揺れ動いた。
「わぁーっ!!!」
「怖がらないで、私に抱きついててくれ」
僕は何が起こったかもわからないまま、目をギュッと瞑ったまま誉さんに抱きついているとようやくボートの揺れがおさまった。
「もう大丈夫だ」
その声に恐る恐る目を開けると、僕たちのボートのそばにもう一隻、男性と男の子の乗ったボートがある。
『Sorry ! I made a careless mista ke!』
『大丈夫。次から気をつけて!』
『ああ、ありがとう』
誉さんと男性が話している横で、僕は少し震えている男の子に声をかけた。
『大丈夫?』
『ぶつかって……怖くて……』
『そうだよね。僕も怖かったけど、抱きしめてもらったら安心したよ。君もパパに抱きしめてもらったらいいよ』
『うん、ありがとう、お兄ちゃん』
男の子はそういうと、男性にぎゅーしてと声をかけていた。
男性は少し驚きながらも、嬉しそうに男の子を抱きしめてあげていた。
ああ、そうか……。
なんとなく、あの二人の関係がわかった気がする。
誉さんはボートを動かしながら、彼らにもう一度視線を送った。
「あの二人、本当の親子になろうとしているところなのかもな」
「そうですね。親子で仲良くなるにはボートの上はいい場所だと思いません?」
「そうかな?」
「ええ。だって、ボートの外には出られないから話ができるだろうし、さっきの僕たちみたいに一緒にボートを漕げば連帯感も生まれますし、一生懸命ボートを漕いでる姿ってすごくかっこいいから、頼り甲斐のあるパパを見せるにはもってこいでしょう?」
「ああ、確かにそうだな」
「僕も誉さんのことかっこいいなって思ってましたし、さっきボートがぶつかったとき、助けてくれたのはすごく頼もしいなって思いましたよ」
「――っ、そうか。なら、私たちも仲良しになれたな」
「ふふっ。そうですね」
あの親子のおかげでなんだか心があったかくなるのを感じながら、僕たちは元の場所に戻った。
ロード中
ともだちにシェアしよう!