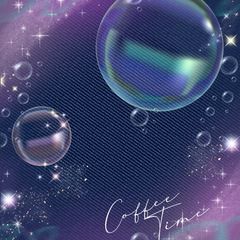28 / 33
思い出を作りに
『怪我はないですか?』
『ああ、大丈夫だよ。問題ない』
僕たちのボートにぶつかるのをみていたんだろう。
誉さんが大丈夫だというと、スタッフさんは安堵の表情を浮かべていた。
チップを払うと、
『怖い思いをさせてしまったのに、いただけません』
と言われたけれど、
『そんなこと言ったら、また来られなくなってしまう。受け取ってくれ』
と誉さんがいうと、ようやく受け取ってくれた。
ぶつかってびっくりしたけど、あの親子も仲良くなれそうだったし、僕の方は誉さんが守ってくれたから怖くはなかった。
また二人で来れたらいいな。
「どこかで昼食でも食べて行こうか」
「はい。そうですね」
「何が食べたい?」
「誉さんが食べたいものならなんでもいいですよ――あっ!」
自分の言葉にふと嫌な思い出が甦った。
「んっ? どうした?」
「いえ、大したことじゃないんですけど……」
「何かあった?」
「あの……以前、由依に同じように何が食べたいかって聞かれて、なんでもいいって答えたんです。そしたら、なんでもいいなんて私のことに興味がない証拠だってものすごく怒られて……僕は、由依が食べたいものを食べればいいと思って僕なりに気遣ったつもりだったんですけどね。それ以来、とりあえず何かを言うことにしてたんですけど、結局僕の意見は却下されるんですよ。気分じゃないとか、それは嫌だとか……結局由依の行きたい店に行くことになって……別にそれはいいんですけど、だったら聞かないでほしいなって……あの時の正解が今でもわからないままです」
僕はそもそも食にこだわりもないし、出されたものに文句は言わないし、アレルギーもないし、なんでも好きだし美味しく食べられるから、本当になんでもよかったんだけど……。
「僕は、相手が食べたいと思うものを共有したかっただけなんですけどね。誉さんも僕がなんでもいいって言ったら腹が立ちますか?」
「ははっ。そんなこと思うわけがない。根本的に考えが違うんだよ、彼女と私は」
「えっ?」
「彼女は、自分が今、何を食べたいか君に察して欲しかったんだろう。自分のことが好きなら、食べたいものだってわかってくれるはずだって思っていたから、君が自分と違うものを言ったときに腹が立ったんだ。だが、魔法使いじゃあるまいし、彼女が食べたいものをピンポイントで当てるなんて無理だろう? そもそも食べたいものなんてその時の気分で変わるものだし、匂いや目にしたものですぐに変わってしまうものだ。当てるなんてできるわけない」
「確かに……」
「だが、私なら宇佐美くんになんでもいいと言われたら、まずは自分が食べて美味しかった店を紹介するだろうな。旅先や知らない場所だったら、気になっていたけどまだ行けていないお店、一緒に行く相手のその時の体調や疲れ具合なんかを考えてすぐに行ける店を一緒に調べて決めたいと思うがな。それが一緒に食事をする醍醐味だと思うけどね」
誉さんの言葉が由依とのあの嫌な思い出を払拭してくれる。
「宇佐美くんが、相手が食べたいと思うものを共有したいっていう気持ちは素晴らしいと思うよ。さっきのジェラートだって、私は多分ここに来るたびに思い出すだろう。宇佐美くんもそうじゃないか?」
「はい。多分一生忘れないと思います。さっきのボートの思い出も込みで」
「ははっ。そうだな。あれはかなりの衝撃だったから」
「それもですけど、誉さんがかっこよかったから……一生忘れないですね」
そう言うと、誉さんは嬉しそうに笑った。
誉さんの中でも今日の思い出が楽しい思い出になってくれたらいい。
「じゃあ、もっと思い出を作りに行こうか。美味しいパスタを出す店があるらしいよ」
「わぁっ! 行きたいです!!」
なんだか、誉さんとだと気疲れしないな。
僕はずっと、一人でいるほうが楽だと思っていたのに……。
誉さんといる時の方がずっとずっと気楽にいられる。
こんなの、初めてだ……。
誉さんが見つけてくれたお店はこぢんまりした可愛らしいお店。
昔ながらの洋食屋さんみたいなそんなお店に入ると、
『好きなところに座って』
と店員さんが気さくに話しかけてくれた。
昼時を過ぎていたからか、お客さんの姿はあまりない。
カウンターからはさっきの店員さんの楽しげな鼻歌が聞こえてくる。
「ふふっ。いいBGMだな」
「はい。これも思い出ですね」
「ああ、そうだな」
二人で話をしながら、テーブルに無造作に置かれたメニューを広げる。
こんなところもアメリカっぽくて楽しい。
「宇佐美くん、何がいい?」
「うーん、悩みますけど……じゃあ、僕、<ゴルゴンゾーラのクリームパスタ>にします」
「じゃあ、私は<魚介のペスカトーレ>にしよう。シェアして食べようか?」
「わぁ、僕ペスカトーレも気になってたんです」
「ふふ、じゃあそうしよう」
誉さんがさっと手を上げると、鼻歌の店員さんがメモを片手に近づいてきた。
『いらっしゃい、日本人?』
『ああ、そうだよ』
『珍しいな、日本人ならあっちの豪華な店に行くのに』
『私たちは旅行じゃないんだ』
『ああ、なるほど。それで何にする?』
料理を注文すると、
『オッケー』
と言いながら楽しげに厨房へと入っていった。
しばらくして美味しそうなパスタが運ばれてきた。
チーズのいい香りに涎が出そう。
いただきますと声を合わせ、パスタを一口食べた。
「――っ!!! これ、すっごく美味しいです!!」
「ふふっ。本当に宇佐美くんは美味しそうに食べるなぁ」
「いや、本当に美味しいですって。誉さんも食べてみてください」
フォークに巻き取って差し出すと、誉さんは嬉しそうに口を開けた。
「ああっ、本当に美味しいな」
「でしょう?」
僕が作ったわけでもないのに、得意げになっちゃってるけど。
「宇佐美くん、エビ食べないか?」
「えー、いいんですか?」
「ああ、ほら、あーんして」
殻を取ったエビを指で口に入れてくれる。
パクッと口に入れるとき、トマトソースがついた誉さんの指が見えて思わず指まで口に入れてしまった。
「あっ、ごめんなさい。指まで美味しそうで食べちゃいました」
「――っ、いいよ。気にしないで」
誉さんはまだ指に残ったトマトソースを舐めてから、紙ナフキンで指を拭った。
それからもお互いに食べさせ合いながら、あっという間にパスタを食べ終わった。
「美味しかったですね、ここのパスタ」
「ああ、ここはまた来たくなるな」
「そうですね」
「じゃあ、そろそろでようか」
さっと伝票を手にしたので、
「あっ……」
というと、
「甘えてくれるんだろう?」
と言われてしまう。
ずっと払ってもらってばっかりでいいのかな……。
なんだか申し訳ない気がするんだけど……。
支払いをしてくれている誉さんから少し離れて待っていると、店員さんとの会話が聞こえる。
『They are a match made in he aven !Be nice to him 』
『Sure !Because it's my sweethe art』
えっ……あれって、僕のことだよね?
sweetheartって……本気?
ともだちにシェアしよう!