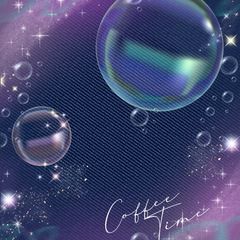30 / 33
全然知らなかった……
「敦己……冗談だと言っても、もう離さないぞ」
僕をギュッと抱きしめる誉さんの手が少し震えている。
同時に胸に押し付けられた耳に誉さんの速い鼓動が伝わってくる。
ああ、僕のこと……本気で思ってくれてるんだな。
「はい。離さないでください」
ギュッと自分からも抱きつくと、
「――っ!!」
誉さんがごくっと息を呑んだのがわかった。
「敦己……このままだと我慢できなくなるから、家に帰ろうか」
「は、はい」
ゆっくりと誉さんの身体から離されていく。
誉さんの温もりが薄くなっていくだけで少し寂しく感じるなんて、僕は自分が思っているよりも誉さんのことが好きなのかもしれない。
「あ、あの……手、は……繋いでてもいいですか?」
「――っ、ああ。もちろんだよ」
差し出された大きな手を握ると、きゅっと包み込まれる。
「誉さんの、おっきいですね」
「えっ?」
「ほら、僕の手とこんなに違いますもん。おっきい方がやっぱりかっこいいですよね」
「あ、ああ。手ね、身長と比例してるからかな。でも、敦己も小さくはないよ」
「あの、なんだか誉さんに敦己って呼ばれると変な感じですね」
「嫌だったか?」
不安げな表情で見つめる誉さんがなんだかおっきなワンコみたい。
「あ、そうじゃなくて……なんか、距離が縮まったみたいで嬉しいなって」
「ああ、そうだよ。恋人になったんだからな。これからもずっと敦己と呼ぶぞ」
誉さん、なんだかとっても嬉しそう。
僕の言葉に一喜一憂するなんてほんとワンコみたいで可愛い。
ふふっ。誉さんが飼ってるコリー犬……ボリスくんって言ってたっけ。
その子もこんな感じなのかな。
手を繋いで歩いていると、行きよりもずっと視線を感じるけれど、誉さんは全然気にしてないみたいだ。
行き交う人もみんな好意的に見てくれているみたいだし、気にする方がおかしいのかも。
まぁロサンゼルスはアメリカでもLGBTには理解がある街だと言われているくらいだし、そもそも日本人カップルなんて気にしないかもな。
手を繋いだまま、社宅に戻ると
『お帰りなさいませ。ボートには乗られましたか?』
と満面の笑顔でジャックに迎えられた。
『ああ、あの公園は雰囲気もいいし、ボートのある湖も最高だったよ。いい場所を教えてくれてありがとう』
『いえ、お役に立てたようで何よりです』
笑顔で見送られながら僕たちは部屋に戻った。
「どうした?」
「あ、いや……ジャック、僕たちが手を繋いでたことに気づかなかったのかなって……」
「いや、十分気づいているだろう。というか、私が敦己の家に泊まりにきた時点で彼らは私が敦己の恋人だと思ってると思うぞ」
「えっ? なんで、どうして、ですか?」
「だって、この部屋には寝室が一部屋しかないだろう? プライバシーを重視する欧米では例え友人であっても、同室で寝るなんてありえないという考えを持っている人が多いからな。お金を持っていないような学生ならまだしも、私がわざわざ敦己の部屋に泊まるのは、恋人以外考えられないと思うよ」
そうなんだ……。
知らなかった。
「じゃあ、キースも?」
「ああ、もちろん。キースはもっと思ってるよ。なんせ敦己と肩を抱いて歩いているところを見ているんだからな。まぁ、最初からそのつもりでやってたんだけど ……」
「えっ、そうだったんですか?」
「ああ、ただの友人と肩を抱いて歩くなんてするわけないだろう? 私が恋人だとみんなに見せつけて牽制してたんだ。あれくらいしていたら、敦己に変な虫が寄ってこないだろう? ただでさえ、日本とアメリカで離れてるんだ。敦己は可愛すぎるんだからそれくらいしておかないと心配だからな」
「誉さん……」
まさかあの行動の裏にそんなことが隠されてたなんて思っても見なかった。
「敦己、呆れたか? まだ告白もしてないうちから牽制なんて……」
「いえ、嬉しいですよ。でも、そんな心配いらないですよ。僕、全然モテないですし」
今までだって、由依以外の人とは付き合ったこともない。
由依だって、僕のことを好きだったわけでもないんだし。
だから、全然心配することなんてないんだ。
安心させようと思って本当のことを話したのに、
「はぁーーっ」
誉さんは何故か僕を見ながら大きなため息を吐いた。
「あの、誉さん? どうかしました?」
「やっぱり紘の言っていた通りだな。自分の魅力を何もわかってない」
「えっ? 魅力? 上田が何か言ってたんですか?」
「ああ。天性のひとたらしだってね」
「ひとたらし?」
「敦己の可愛い顔を好きになるのはもちろん、一緒に仕事をすればその優秀さにどんどん惹かれるし、内面も外面も申しないって。だから、営業で外に行くたびに担当先の社員に敦己のことを聞かれると言っていたぞ」
「そんな……」
上田がそんなことを誉さんに?
なんか……恥ずかしい。
「紘はそんな敦己に近づこうとする奴らをかなり排除していたらしいよ。知らなかっただろう?」
「えっ、全然知らなかったです」
「だろうな。敦己があの彼女と出会うきっかけになった飲み会の時は、紘が出張に行ってて排除できなかったって。元々、あの彼女がくる予定じゃなかったんだろう?」
「はい。そうです。突然、予定の人が来られなくなったからって……」
「紘はかなり心配していたよ。敦己が騙されてるんじゃないかって」
「あの、誉さんはいつから僕のことを知ってたんですか?」
「敦己が彼女と付き合いだした頃からかな。紘に相談されて、もし何かあったらすぐに相談に乗ってやってほしいって頼まれてたんだ」
「だからあの日、すぐに来てくれたんですか?」
そう尋ねると誉さんは大きく頷いた。
ロード中
ロード中
ともだちにシェアしよう!