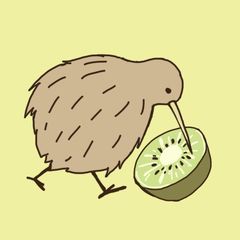
『ラブ、大盛つゆだくで』 累計リアクション4000 over 感謝短編.。*゚+.*.。【2】
https://fujossy.jp/notes/26180
の続きです。(全3話)
既読の方向けのコンテンツになりますので、本編読了後にお楽しみいただけたら幸いです。
たくさんのリアクションどうもありがとうございました♡
『ラブ、大盛つゆだくで』(完結済)
https://fujossy.jp/books/17547
【お礼置き場】
https://fujossy.jp/notes/23365
それでは、どうぞ ↓
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( ※ 本編ネタバレ注意!! )
『あの素晴らしいラブをもう一度 #2』
「来ちゃった」
そんな可愛らしい言葉と共に、一人残業している恋人のもとへ牧が文字通り押しかけてきたのが、つい先程のことで。
これまでも客として幾度か鳴海の職場に足を運んでいた牧だったが、閉店した美容室へ入るのはさすがに初めての経験のようで、薄暗い店内を物珍しそうにきょろきょろと見回している。
手にぶら下げられたビニールの手提げが、牧が体の向きを変える度に、それが振り子のようにゆらゆらと揺れた。
今となってはすっかり馴染みの深い醤油と出汁のいい香りが、まだ夕食を口にしていない鳴海の鼻をくすぐるが。空腹であるということを忘れてしまうくらいに、今の鳴海の意識は完全に目の前にいる牧へと向けられていた。
――これは、夢なのか…?
「……鳴海? 何してんの?」
「いや。その。……。俺はいつの間に眠ってしまったんだろうと、思って…」
「もしかして、これ夢だと思ってる? あ。だから自分の頬つねってんのか? はは、鳴海おもしれー」
そう言って、牧が楽しそうに笑った。
つねっていない方まで赤くなってしまった頬を隠すように、鳴海は照れ臭そうにその大きな手で口元を覆った。
「だって。まさか、こんな時間に牧さんが来てくれるなんて…。今日はもう会えないんだと思ってたから。……来るなら、連絡くれればよかったのに」
「連絡なら、ちゃんとしたけど?」
「えっ」
慌てて、カウンターの上に置きっぱなしにしていたスマホを確認する。
作業に集中していて、見逃してしまっていたのだろうか。
しかし、そこには新着の通知は一件もなく。
鳴海は頭の上に疑問符を浮かべながら、視線を画面から牧へと戻すと。
「さっき電話で、『またな』って言っただろ」
「え…。あれって『また今度』じゃなくて、『また後で』って意味だったの……?」
言われて、先程の電話でした最後のやり取りを思い出す。
てっきりよくある別れの挨拶のつもりでいたが、どうやら言葉の意味を履き違えてしまったらしい。
鳴海が動揺を隠せずにいると。しばらくして牧が吹き出し、その表情を崩した。
「ごめん。嘘だよ、嘘。本当は、鳴海を驚かせてやろうと思ってさ。……びっくりした?」
「うん。びっくりした…。でも、牧さんに会いたかったから、嬉しかったよ」
昔からサプライズは得意な方ではなかったけれど、こういったことならいくらでも大歓迎だ。
「あっ、そうそう。牛丼。持ってきたんだ。鳴海、きっとお腹空かせてるだろうと思ってさ」
牧が、持っていた白いビニールの手提げ袋を受付カウンターの上に置く。
そういえばさっき『Oder Eats』の真似事をしていた時も、そのようなことを言っていたような気がする。
ありがとう、と礼を言って袋の中身を確認すると。いつもの牛丼屋でテイクアウトしたという、プラスチック容器に入った牛丼弁当がそこにあった。
「2つあるってことは…。もしかして、牧さんも晩御飯まだ食べてない?」
「うん。まぁね」
「先に食べててくれても良かったのに。牧さんだって仕事だったんだから、お腹空いてたでしょ」
「別にこのくらい平気だよ。――それに俺、やっぱり鳴海と一緒に食べたかったからさ」
「牧さん……」
「それで? 仕事は、もう終わりそうなのか?」
牧が、電源が入ったままのタブレットの液晶画面をひょいと覗き込む。
「あぁ、うん。仕事のほうはちょうど今終わったとこで――…」
言いかけて。
鳴海は、あることを思い出す。
――しまった。最後に見てた画面って、確か…!?
慌てて電源スイッチをオフにしようとするが、既に手遅れのようで。
「鳴海って、本当に俺のことが好きだよなー」
「……これは、その。目の保養……というか…」
一人でこっそり牧の写真を観賞していたのが見つかり狼狽する鳴海を前に、なぜか牧は至極ご満悦の様子で。自身がモデルとなった画像を、口角を上げてニンマリと笑みを浮かべながら、嬉しそうに眺めている。
そして鳴海は、画面の中にいる牧のアプリコット・オレンジの髪と、生身の牧の姿とを改めて見比べて。これまですっかりタイミングを逃してしまっていた疑問をひとつ、投げつける。
「ねぇ、牧さん。ずっと気になっていたんだけど……。その髪の色、どうしたの?」
「あぁ、これ? さっき家で自分でやったんだ。カラートリートメントってやつで、一時的に黒くしただけなんだけど」
カラートリートメントというのは、髪の表面にだけ色をコーティングするタイプの染料のことである。髪の内部に色素を入れる一般的なカラーリング剤とは違い、表面にだけ色を付けるため、シャンプーの度に染料が落ち、使用を止めれば大体1〜2週間ほどで元の髪色に戻っていくというものだ。
色持ちはあまり良くない上、ブリーチをしていない髪には色が入りにくいなどのデメリットもあるが、自宅でインスタントにカラーチェンジできる手軽さと、トリートメントなのでヘアケアも同時に行えることから、昨今では利用する者も多いようだ。
「この前、鳴海の話を聞いて…。あれからすぐ買いに行ったんだ。いつでも髪を黒くできるように、準備しとこうって思って。前にそういうのがあるって、うちの職場で聞いたことがあったからさ。……でも、なかなかタイミングが掴めなくて、どうしようかと思ってたんだけど」
話、というのは。
鳴海が牧に一目惚れして、勝手に何年も片想いをしていたというあの恥ずかしい暴露話に違いない。
しかし、そのことと髪を黒くすることに、何の因果があるのだろうか…。
「そしたらさ。新人の研修で鳴海の髪がストレートになったっていうじゃん? あー、これはもう今日やるしかないなって思って」
「ちょ…、ちょっと待って牧さん! 不思議に思ってたんだけど、どうして牧さんは今日うちに新人が入ったことや、俺の髪がストレートになってることを知ってたの…? 俺、話した覚えはないんだけど……」
「なんか知らねえけど、お前んとこの先輩とやらがわざわざ教えてくれたんだよ。昼間、『今日入った新人スタッフの研修に付き合って、鳴海くんは今ストレートヘアになってまーす♡』ってメッセージが送られてきた。写真つきで」
「えっ。いつの間に……」
盗撮されていたこともそうだが、知らないうちに同僚の一人が牧と連絡先を交換していたということに衝撃を受ける。
何それ。聞いてないんだけど…。
「その新人っていうのが女ならまだしも。男だっていうから、不安で。なんか俺、居ても立っても居られなくなって」
「……?? どうして、男だと不安なの?」
「だって鳴海、元々ゲイだったんだろ。そいつが男なら、惚れる可能性だってあるわけだし」
「そんな簡単に、惚れないよ」
「でも俺のときは、いとも簡単に恋に落ちたじゃねえか」
「それは、相手が牧さんだからだよ。男だったら誰でもいいわけじゃないから。その理論でいったら、世界の人口の半分が恋のライバルになっちゃうでしょ」
「まぁ…。確かにそうだけどさ……」
口を尖らせて拗ねたような表情を見せる牧を前に、鳴海は口元が緩むのを抑えきれずにいる。
自分の可愛い恋人は、時々こうして嫉妬や独占欲を剥き出しにしてくれる。それが嬉しくて、堪らない。
だって、相手を好きでなければそんな感情が生まれることはないのを、知っているから。
つまり、それだけ愛されているという証拠だ。
……そんなことを考えながら、一人、幸せに浸っていると。
「なぁ、鳴海。今日の俺の格好見て、何か思い出さない…?」
牧の瞳が、眼鏡のレンズの奥から鳴海をまっすぐ捉える。
これは、何か答えを期待している時の目だ。
相手の真意は掴めないままだが、鳴海は、ただ素直に思ったことをそのまま口にする。
「6年前。牧さんが客として俺の前に現れたときと、同じ格好だね」
黒髪に、眼鏡。
白いTシャツ、黒のスキニー。そして、ベージュのカーディガン。
ずっとその姿の牧さんを――その影を、何年も追いかけていたんだ。忘れるわけがない。
「そう。そしてお前は今、いつものウェーブヘアではなく、ストレートヘアと来ている。――つまり、俺たちが初めて出会ったときのビジュアルと、ほぼ同じということだ」
鳴海の話だけを手がかりに当時のコーディネートを思い出すのに苦労したんだ、と牧は熱く語る。
「――要するに、俺が何を言いたいかっていうと」
一旦、そこで言葉を区切ると。
牧は、かけていた眼鏡をカウンターの上に置き。それから鳴海の腕を掴んで、店の奥にあるシャンプー台へと引っ張っていく。
「今日、ここで。俺たちの出会いをやり直そう」
そう言って。
牧はシャンプー椅子に自ら体を預けた。
あの時を、やり直す?
俺と牧さんが、出会ったシーンをもう一度……?
「えっと…。あの時みたいに。シャンプー、すればいいのかな?」
「いや。シャンプーはさっき家でしてきたばっかだから、それはいいよ」
「えぇっ…」
シャンプー台でシャンプー以外のことなんてした経験がないので、当惑する。
何をすればいいのかわからないまま、とりあえず椅子を後ろに倒すと、自然と牧の体も座る体勢から寝そべる形へとなる。そしてあの時と同様に、牧は胸の前で指を絡めながら手を組み、静かに目を瞑った。
こうして見ると、本当にあの時と同じみたいだ…。
間接照明の薄明かりが牧の綺麗な顔の輪郭を照らし、瞼を閉じたその姿はまるでおとぎ話の眠り姫のようだと、いつか抱いた第一印象まで鮮明に蘇る。
しかし、記憶通りに物語をなぞるのはここまでのようで。
「鳴海。あの日俺のこと何も聞けなかったのを、ずっと後悔してたって言ってたよな。だから今、思う存分、好きなだけ質問していいよ」
ふふん、と得意げに牧が言う。
どうやら、ヘタレすぎて何もできなかった自分を気遣って、わざわざこうして親切にイベントまで用意してくれたらしい。
確かに、名前も住んでいるところも職業もあの時聞いてさえいればもっと早く探し出すことができたのにと、あれから何度も自分を責めた話を、牧にしたような気がする。
……やっぱり牧さんは、優しいな。
胸の中がじんわりとあたたかいものに包まれるのを感じながら、すうっと大きく息を吸った。
「はじめまして。俺、鳴海といいます…。音が鳴るの『鳴』に、さんずいの『海』と書いて、ナルミと読みます」
「へー、鳴海さんて言うんだ。俺は牧場の『牧』で、マキっていいます。二人とも、音だけだと女の子に間違えられそうな名前してるね」
はは、と笑いながら、牧は過去に何度も話題になった鉄板ネタを持ってくる。
それがなんだかおかしくて、次第に鳴海も楽しい気持ちになってきた。
「牧さんは、おいくつなんですか?」
「あー。この時空で言ったら、24…かな。本当は30だけど」
「そうですか。俺もこの時空だと、22なんで。どちらにせよ、2歳差なのは変わらないですね。お住まいは、どのあたりですか?」
「家はここから2駅先の、暁ヶ丘ってとこ。そこの駅ビルに入ってる『invisible garden』っていう服屋で働いてるんだ。よかったら、今度遊びに来てよ」
「行きます。絶対、行きます。必ず行きます。……あ。俺は、美容師をやってます」
「知ってる。ここ、美容室だし」
「あ、ですよね……」
あぁ。二度目のイベントですら、会話の選択肢を間違えるなんて…。
牧は笑いを堪えるほど面白がってくれているが、この調子じゃ当時同じ質問をできていたとしても、ただの挙動不審な男で終わったかもしれない。
「……ちなみに牧さんは今、つき合ってる人はいるんですか?」
「今はいないよ。…まぁ、本当にいなかったんだけどさ。でも、そのうち俺のことを物凄く好きなヤツが現れて、俺もそいつのことを好きになるような気がする。てか、予定?」
「……その相手は、どんな人だと思いますか?」
「そうだなぁ…」
そこで牧は、それまで閉じていた瞼をパチリと開け。
「お兄さんみたいな人だったら、嬉しいかな」
そう言って、鳴海の腕をグイと引いた。
不意打ちだったため鳴海は体勢を崩して、咄嗟にシャンプー椅子に片手をつき倒れないように堪えるが。結局、牧の上に上体が覆い被さるような形になる。
一気に縮まった距離に、出会ったあの日と同じようにドクドクと心臓の鼓動が速くなっていく。
「牧さんは…。俺みたいなのは、タイプですか……?」
こんな質問、当時だったら絶対にできないが。
今なら、怖くはない。というか、ここまで来たらもうヤケだ。
「うーん。俺、眼鏡外しちゃってるから、今ちょっとよく見えないんだよね。もっと顔、こっちに近づけてもらってもいい?」
「……こうですか?」
「ダメ。もっと」
「このくらい…?」
「もっと…」
「……」
お互いの吐息がかかるくらいの距離まで、近づいたところで。
「うん。やっぱ、お兄さんの顔。俺の好きなタイプだわ」
掠れた声で、牧が囁き。そして。
鳴海の頭を手で押しつけるように引き寄せ、その唇にキスをした。
「牧、さ……っ!? んッ…」
ぬるりと侵入してくる舌に戸惑ったのは最初だけで。
すぐに鳴海も、いつものような深い口づけで牧のそれに応えていく。
無我夢中で口の中を舐めて、吸って。
しばらく、チュクチュクと唾液の絡まる音が続いた後。
――いけない…。これ以上は、もう……。
鳴海は必死で、心地よい感覚から逃れるように体を離すが。
理性が性欲に打ち勝ったのはほんの一瞬だけで、目の前の光景に、すぐに本能を呼び戻されてしまう。
「鳴海…。俺、さっきシャワー浴びたとき、準備してきたんだ……」
何を、と聞くよりも早く。
牧が横たわったまま、穿いていた黒のスキニーを下着ごとズルンと下ろし、膝裏を自ら抱えて足を開く。
その中心では、上を向いた茎がピクピクと小刻みに震え。
そして曝け出された薄紅色の蕾は、そこへ誘うように厭らしい蜜を垂らしている。
「牧、さ……ん…」
徐々に呼吸が荒くなっていく中で、鳴海は生唾をゴクンと飲み込んだ。
体が。熱くなっていく。
喉が渇いて水を欲するのと同じように、牧を抱きたいという欲望が当然のように湧き出て来る。
あぁ。思い出した。
初めて会ったときから。ずっと。俺は。
この人に、心も体も支配されていたんだ――…。
「ねぇ、鳴海」
牧がカーディガンのポケットからコンドームをひとつ取り出し。
それから、そのパッケージにチュッと触れるだけのキスをした。
とろけるような視線が、鳴海の体に纏わりつく。
「今、ここで…。えっち、シよ……?」
(つづく)
