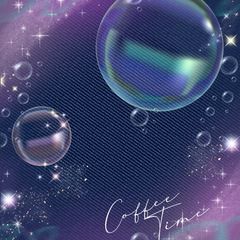23 / 85
ネクタイと汗
『キース、ここで少し待っていてください』
『はい。承知しました』
支社の前でさっと降ろされるだけだと思っていたのに、なぜか透也くんは一緒に車から降り出した。
「えっ? どこまで行くんだ?」
「心配なので、中に入るのを見届けます」
「心配って……子どもじゃないぞ」
「わかってますよ。俺が離れるのが寂しいだけです」
「――っ!! そ、んなこと……っ」
誰が見ているかもわからない会社の前で言うなんて……。
透也くんは男と付き合ってるなんてバレても気にしないんだろうか?
「お昼に迎えに来ますから、どこにもいかないでくださいね」
「ああ、わかってる」
「じゃあ、大智さん。いってらっしゃい」
笑顔でポンとネクタイに触れられてドキッとする。
そういえば、今日のネクタイは透也くんのだったんだ。
俺がセキュリティーゲートを通るまで見送られて、最後に振り返った時には笑顔で手を振られた。
そして、今度は俺が透也くんがキースの車に戻っていくのをそっと見送っていると、
「支社長、おはようございます」
と声をかけられた。
「えっ、あ、ああ。おはよう」
「あの方、お知り合いですか?」
「ああ。傘下企業の子だよ。短期出張できている間、同じ社宅に住んでいるんだ。だから一緒に車で来たんだよ」
「へぇ、そうなんですね。あれ?」
俺の顔あたりを見ながら、突然不思議な声をあげる彼女に驚いた。
もしかしたら、透也くんとのことがバレるような何かがあったのかと一瞬冷や汗をかきながら、それでも
「どうかした?」
と冷静を装って尋ねた。
「いえ、支社長のそのネクタイ……」
「えっ? ネクタイ?」
「すごくお似合いですね。なんだか、いつもと系統は違いますけど、すごくよくお似合いです。あ、もちろん、今までのも似合ってましたけど、このネクタイは今日のスーツによく合ってて……あっ!」
野崎 さんは突然目をキラキラさせたかと思ったら、ニマニマしながら
「もしかして……彼女さん、からの贈り物ですか?」
と言ってきた。
「えっ……」
「ふふっ。やっぱり。支社長、わかりやすすぎですよ」
「いや、ちが――っ」
「はいはい。じゃあ、そういうことにしておきますね。でも、本当にお似合いですよ」
そう言って野崎さんは楽しそうにスキップでもしそうな勢いで、受付に向かっていった。
何がそんなに嬉しかったのかわからずに立ち尽くしていると、
「支社長?」
とセキュリティーゲートを通ってきた部下の子に声をかけられて驚いてしまった。
「あ、ああ。おはよう」
なんでもないふりをして、自分のフロアに向かった。
仕事をしながらも、気になるのはネクタイのことばかり。
なんせ、仕事の話に来るついでにみんながネクタイのことばかり尋ねてくるんだから。
似合っているのは嬉しいけど、そんなに今までのネクタイと違うかな?
そこまで変わらないと思ったんだけどなぁ……。
でも……外したいとは正直言って全然思わない。
なんとなく、透也くんがそばにいてくれているような気がして、安心するんだ。
心なしか仕事もよく捗る気がする。
透也くんのネクタイで仕事がスムーズに行くなら、験担ぎみたいな感じで毎日借りるのもありかもしれないなぁなんて、思ってしまう。
まぁ、今日だけ特別なんだとは思っているんだけど。
でも一度頼んでみようかな。
例えば……
――透也くんのネクタイ、すごく評判がよかったんだ。よかったら、明日からもネクタイ貸してくれないか?
いや、流石にそれは図々しいか……。
なら……
――透也くんのネクタイ、すごく評判が良かったから今度一緒に選んでくれないか?
うん、これならイケるかも!
今日、お昼に会う時早速頼んでみようか。
そんなことを考えているとなんとなく楽しくなってきて、あっという間にお昼近くになっていた。
アメリカの企業ではランチ時間が短かかったり、長かったりそれぞれ違いはあるけれど、こちらは日本企業の支社ということもあって、しっかりとランチタイムをとっている。
ハンバーガーやピザ、タコスなどのデリバリー定番ものもあれば、最近は店の料理をそのまま持ってきてもらうことも多い。
とはいえ、こういう食事が楽しいのは最初の1、2週間くらい。
それ以降は、結構お弁当を作って持ってきている人も多い。
俺も最近、飽きてきていたところだったから、透也くんの料理には本当に感謝している。
その透也くんがおすすめだという店なら、かなり期待が持てる。
どこのランチに連れていってくれるんだろう……。
逸る気持ちを抑えながら、
「ランチに行ってくるよ」
と声をかけてロビーへと向かった。
少し早かったな。
外に出て待っていた方がいいかな……なんて思いながら、セキュリティーゲートを通っていると
「大智さんっ!!」
と透也くんの声が聞こえた。
「あれ? もう来ていたのか?」
「はい。午前中外回りに行っていたので、そのまま来ました」
「ああ、だからか、少し汗をかいてる」
「えっ? すみません、汗臭かったですか?」
「いや、それは全然気にしないよ。むしろいい匂いしかしてない」
「――っ!! 大智、さん……っ」
「んっ? どうかしたか? 顔が赤くなってる。やっぱり暑かったんだろう?」
急に顔を赤らめた透也くんが心配で、ポケットからハンカチを取り出して透也くんの首筋を流れる汗を拭き取った。
「仕事、お疲れさま」
汗を拭きながら、そう声をかけると透也くんはさらに顔を赤らめた。
ロード中
ロード中
ともだちにシェアしよう!