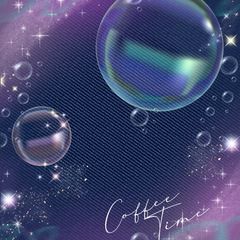21 / 33
誉さんとの約束
「ところで、伊山由依さんの件だが……」
ああ、やっぱりその話が来た。
ないわけないもんな。
真剣な表情で僕を見た誉さんは、持っていた鞄から少し大きめの封筒を取り出した。
まだ時間がかかっているんだろうな。
婚約破棄とその他諸々の手続きやなんかがあるんだからそんな簡単に終わるわけがない。
それに由依がすんなり引き下がるとも思えないしな。
何か書類でも書くんだろうかと思っていると、出てきたのは銀行の通帳。
「あれ? これは……?」
「伊山由依さん、新島賢哉さん双方からの慰謝料。そして、宇佐美くんが購入した指輪やマンションローンの頭金などの弁済金が満額入ってる」
「えっ? あの、金額が満額、ですか?」
「結婚式場へのキャンセル料はここからすでに式場に支払い済みだよ。これが領収書だ。通帳の中身と一緒に確認してくれ」
渡された通帳を開いてみると、確かにあの内容証明に記載していた通りの金額が納められていた。
「こ、こんなに早く……しかも、一括でなんて……」
「ふふっ。実はね、こっちにくる前に二日ほどこの件だけに絞って動いていたんだ。君に会う時には全て解決しておきたかったからね。君が傷ついた心はこんなお金じゃ元通りにはならないだろうが、少しは気が楽になっただろう?」
あの嫌な光景を忘れようとしてもなかなか頭から離れてくれないのは事実だ。
だけど、由依とのことどころか、あの家のことまで全て方がついたのは嬉しさしかない。
これで安心して日本に帰ることができる。
あと一つの懸念を残しては……。
「誉さんっ、ありがとうございます! 僕、なんてお礼を言ったらいいか……」
「お礼なんて、今回こうやって宇佐美くんの家にお世話になっているんだからこれでおあいこだよ」
「誉さん……」
「これで君には何の憂いもなくなった。彼女たちと会うこともおそらくないだろう」
「あ、でも仕事先が……」
そう。
僕の一つ残った懸念材料はこれ。
元々仕事先の飲み会で由依と出会ったんだ。
うちの会社と繋がりがないわけじゃない。
しかも、浮気相手の男は由依と同じ会社だと言っていた。
「ああ、それも大丈夫。彼らは二人とも懲戒解雇になったんだ」
「えっ? 懲戒解雇? どうしてですか? 僕とのことで?」
「違うよ。元々の彼らの素行の問題だ。調査の途中で彼らが仕事時間中にホテルに入り浸っていたのがわかってそれが問題視されたんだ。だから、宇佐美くんのこととは無関係だよ。君が気に病む必要はない」
「そうなんですね……。僕、何も知らなくて……今回誉さんに全てをお願いしてよかったです。由依の事実を知れば知るほど、結婚する前でよかったって思えるようになったから」
「ああ、そうだな。君の綺麗な戸籍が無駄に汚れなくてよかった。次に結婚するときに何も気にしないでいい」
「えっ? 次……?」
「ああ、いつかは宇佐美くんも、結婚するんだろう?」
誉さんにそう言われて、僕はなぜか頭が真っ白になっていた。
それくらい今回の由依とのことがトラウマになってしまっていたのかもしれない。
「結婚は、もういいかなって思ってます。元々あんまり恋愛には向いていないのかもしれないです」
「そうなのか?」
「はい。由依とのときは……って、もう忘れたほうがいいですよね」
「一人で抱え込んでるより全て話してスッキリしたほうが早く忘れられるよ。宇佐美くんの心の中を全部聞かせてくれ。私はどんなことでも受け止めるよ」
「誉さん……」
そんな優しい言葉をかけられたら、泣いてしまいそうになる。
だけど、誉さんに涙は見せたくない。
まだ由依のことを思っていると勘違いされたくないから。
「取引先との飲み会に急遽参加することになった由依と出会って、ぐいぐい押されている間にいつの間にか連絡先交換していて、それから毎日のように連絡が入るようになったんです。今までこんなふうに積極的に来られたことがなくて、戸惑っている間にいつの間にか付き合うことになってました」
「そうだったのか」
「はい。でも、付き合うと言っても、僕から連絡したことはほとんどなくて大抵が由依から映画に行きたいとか、買い物行きたいとか言われたのに付き合うって感じで……今までとは全然違う休日の過ごし方に最初は新鮮だなと思いました。でも、僕は基本家にいるのが好きなんでだんだん疲れてきちゃったんですよね。それでその話をしたら、本当は由依もそっちがよかったみたいで、付き合うことに慣れていないから頑張って誘ってたんだって言われて……」
「なるほど」
「それからは、お互い気が向いた時に出かけるくらいで。でもそれくらいの距離が僕にとっては居心地が良かったんです。結婚してもお互いに気楽に過ごそうって言われて、そんなこと言ってくれる人はいないでしょう? 両親から結婚の話もちらほら出てきていたし、面倒な人と結婚することになるくらいなら由依の方がいいって結婚を決めたんです。だけど、今思えば由依にはあの男がいたから、ATMがわりに存在してくれる人なら誰でも良かったんですよね。悲しいですけど、でも僕も打算で付き合ってたんだから、由依のことを文句言えなかったかも……」
由依があんなにも長い間、他の男と付き合ってたことに気づけなかったのも、僕がそもそも由依に興味がなかったからなのかもしれない。
「でも、宇佐美くんは少なくとも彼女を裏切ろうとする気持ちはなかっただろう? 彼女のために仕事も頑張っていたじゃないか? 結婚していたら、きっと大切にしていたはずだ。だが、彼女は最初から宇佐美くんを裏切っていたんだから、彼女と君は全然違うよ」
「誉さんにそう言ってもらえて、少し気持ちが楽になりました。でも……僕、結婚はもういいです。誰かと一緒に暮らすなんて最初から向いてなかったのかもって思うんです。だから……僕が、帰国したら居候させていただく話ですけど……誉さんに迷惑かけちゃうかもしれません。やっぱりお断りしておいたほうがいいのかも……」
「いや、それは違うよ」
「えっ?」
「宇佐美くんは誰かと一緒に暮らすことが向いてないんじゃない。気を遣いすぎて疲れてしまうんだよ」
確かに言われてみればそうかも。
由依が何度か泊まりにきていたときも、由依が機嫌悪くなっていないかばかりが気になって、由依が帰ったあとどっと疲れていた気がする。
「宇佐美くんは誰かに甘えることに慣れていないのかもしれないな。もしかして宇佐美くんはひとりっ子なのかな?」
「はい。そうです」
「そうか、やっぱりな。紘はなんだかんだ言いながら困った時には私に助けを求めてくるんだ。だが、宇佐美くんは自分から助けを求めたりしないだろう? 今回だって、たまたま紘と出会ったから話をしたんじゃなかったか?」
「そう、ですね……」
あのとき、道端でどうしていいかわからなかった時に、声かけてくれたんだった。
あの時上田がいなかったら、きっと誰にも相談することなくこっちに帰ってくるしかなかったろうな。
「なら、練習したらいい」
「練習、ですか?」
「ああ。これからは私に何も気を遣わず甘えてくれないか?」
「えっ、誉さんに? でも……」
「紘同様に私のことを兄だと思えばいい。弟はなんでも甘えてくるものだぞ」
誉さんをお兄さんだと思って、か……。
確かにずっと上田が羨ましいと思ってた。
うん、女性に甘えるのは無理そうだけど、誉さんならできるかも。
「わかりました。じゃあ、甘えさせてもらいますね」
「ああ、どんどん甘えてくれ」
「ははっ」
「ふふっ」
楽しそうな誉さんの声に僕も久しぶりに声に出して笑った。
ともだちにシェアしよう!
この作品を読んだ人におすすめ
不憫魔導王子は、魔王と成り上がる❗
連載中
R18 イケメン×筋肉質平凡