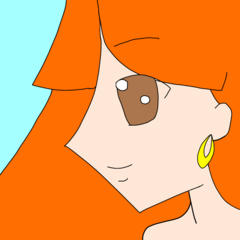人気のタグ
人気の小説
たとえ、君が覚えていなくても。たとえ、僕がすべてを忘れてしまっても。それでもまた、君に会いに行こう。
性奴隷にされた美少年が鬼畜な羞恥凌辱の果てにメス堕ちする物語。
ヤンデレ社長年下上司×天然鈍感年上部下
ゲイは絶対秘密なのに、男とラブホ入るとこを後輩に見られた…。
連載中
1947年7月、東京。U機関のクリアウォーター少佐とカトウ軍曹らは、新たな事件に遭遇するーー。
人気の漫画
happyHalloween♡
可愛いくても やっぱり男の子…なショートショート♡
おじ騎士さんとお弟子くん
両片想い&年の差師弟のほのぼのな日常です。
初恋アラート
大柄わんこ系×年上恋愛下手
2時間カレシ
レンタル彼氏に恋をしてしまうBL漫画です
お仕置き中の受けちゃんを肴に酒を飲む攻めっていいよね
お仕置き中の希望を肴にライが酒を飲むのは一コマしかないぞ
たぶん!絶対 君と出逢うために生まれてきたんだと 僕は信じてる!
わりと悲惨な生い立ちのサンは お隣に引っ越してきた芦毛さんに一目惚れをする
Triangle
高校生三人、、、それぞれの過去と思いが交差する
お狐様【マンガ】
昔々あるところに、変化の得意なお狐様がおったそうな。
人気のイラスト
初めての方へおすすめ
竜神と御曹司の甘く淫らな妖怪譚
連載中
書籍あり
やっと再会できた親友に何故か拒絶されてしまった。平凡受け/学園オメガバース。
連載中
R18 Dom/Subユニバース設定の作品です
新着アトリエブログ
春節の準備をしませんか?
こんばんは、荷蓮花です。 12月~2月にかけて、マイページを冬バージョンにしております。クリスマスからバレンタインデーまで、イベント目白押しのこのシーズンに合わせたお話を並べております。 ...
センシティブな話
いつも拙作にリアクションして頂き、ありがとうございます。 亀更新で申し訳ありません。『幻夢』の最新ページを公開致しました。 *** アゲ散るシリー...
本日1/21の更新
いつも「ぬきさしならへんっ!」を読んでくださってありがとうございます。本日1/21の更新は朝の1回のみとなります。明日また新しい話から更新します!よろしくお願いします〜
新連載「連理の枝が折れる音」
ちょこっと書いて年末に発表するつもりだった。 お正月休みに読んでもらおうと。 とんでもないことである。 とっくに松も取れて成人式も済んだのに話は終わっていないのだ。 しかしそろそろ...
おまたせしました!「蒼く光る」更新です!今年最初の更新
お待たせしました。今年最初の更新です。 P28~P35まで8頁更新です。新章「そして、今」#1~#8の更新となります。この章はこれで終わりで次はまたあたらしい章です。次は全章にわたり暴力...
fujossy運営ブログ
【お知らせ】サポート窓口休業期間について
2024/12/19
【第四回fujossy小説大賞】第二次選考発表!
2024/12/13
【第四回fujossy小説大賞】第一次選考発表!
2024/10/31
【ご利用の皆さまへ重要なお知らせ】リアクションボタン仕様変更について
2024/7/18